
三笠哲也
shape of heart
(2022年時点)
| CP | 17 |
| NP | 13 |
| A | 17 |
| FC | 12 |
| AC | 15 |
三笠哲也さんのエピソード集です(読みたいタイトルをクリックしてください)
神楽坂美咲との出会い 第一章
三笠哲也
(20歳当時)

帝香山大学が誇る「日本文化研究ゼミナール」。通称「崎山ゼミ」。
そこに異例ずくめのルーキーが入ってきた。
名前は、神楽坂美咲。1年生。
通常、このゼミは2年生の後期からでないと入れない。しかもかなり厳しい試験がある。
では、なぜ?
神楽坂の場合、高校の時に出した論文に、担当教授の崎山がいたく惚れ込み、教授自らが特例としてスカウトしたそうだ。
それだけでもザワつくのに、神楽坂は5日ほど前から毎朝TVに出始めたお天気キャスターだった。

【学内で一番注目を集めるホットな人間が、今、目の前に…】
ゼミ生15人の目には、興味と疑念、好意と反感が複雑に入り混じっていた。
そんな中、神楽坂は淡々と落ち着き払った様子で挨拶を終えた。
その姿は、先月まで高校生だったとは思えないほど大人びていた。
崎山が満足そうな笑みを浮かべた後、口を開いた。
「おーい、三笠君」
指名された三笠哲也が音もなく立ち上がった。
美形でクールだが、少しお高くとまっていて、お世辞にも人付き合いが良いとは言えない3年生だった。
「まぁ、さすがに神楽坂さんも勝手が分からないだろうから、しばらくは副ゼミ長の君が色々と教えてあげてくれ」
「分かりました」
三笠は颯爽と答えると、音もなく座った。

翌日。
ゼミが始まる30分前に、三笠は神楽坂へ、活動の簡単な説明をした。
1、基本的には、個人が日本文化の文献を調査研究し、それに基づいた論文を執筆すること。
2、フィールドワークとして、伝統的な祭りや催し、歴史的な建造物、芸術イベントなどを見に行く点。
3、専門家や実践家を招いてゲスト講義を行ってもらうこともある点。
4、それぞれが自分の研究進捗やアイディアを発表し、学生同士や教員とのディスカッションを行うこと。
背筋をピンと伸ばして聞いていた神楽坂の反応を見て三笠は判断した。
多分、理解が早いのか、つまらなかったのかのどちらかだろう。
彼女は「はい」と「分かりました」だけを繰り返し、質問はないまま、最後に深くお辞儀をしたのだった。

ゼミが始まって1週間が経った。
神楽坂は、三笠哲也という人間が、自分の教育係についてくれたことに感謝していた。
今は大学のどこにいても注目され、色々な人間から声をかけられ、同じような質問をされ、様々な誘いを受ける。
それがとても煩わしかった。
しかし三笠は全く自分に興味を示さない。
必要なことだけを簡潔に教えてくれる。
それがとても安心できた。
そして下世話な騒音ばかり入ってくる今の自分にとって、三笠の無駄のない洗練された日本語が、耳に心地よかった。

1か月後
神楽坂は、ゼミに関する質問がある時だけ三笠に尋ね、三笠は、神楽坂に聞かれたことだけを答え、自分から話しかけることはない。
いつしかそんなルールや関係性ができあがっていた。
三笠の中では、「もう教えることはない」という感覚があったのも事実だ。
そんな中、崎山ゼミにおいて、2つのグループに分かれてのディスカッションが行われた。
神楽坂にとってはデビュー戦。
そこで執拗に叩かれた。
新人への洗礼の意味もあったのか、嫉妬なのか、神楽坂独特の解釈に納得できなかったのか…、時に理不尽と思えるような批判も出た。
それを1時間だ。
先輩によるいじめとは思わなかったが、不毛な時間を建設的に変えようともがいた神楽坂にとっては、長い長い1時間だった。

ディスカッションを終えた神楽坂は、失意のまま退出した。
色々と思うところはある。そして得たものはない。
いつもは前を見据えて歩く神楽坂だが、珍しく俯きながら、第三校舎の廊下を速足で歩き続けた。
すると突然、その頭を上から軽く撫でる者がいた。
「お疲れさま。よく1人であんなに頑張ったね」
少し息を切らした聞き覚えのある声。
顔を上げると三笠哲也だった。
どうやら後ろから追いかけてきたらしい。
ただ、いつもはクールで物静かな三笠なのだ。
こんなことをするイメージがなかったので、神楽坂は少し戸惑った。

神楽坂は、髪に三笠の温もりが残る中、疲れ果てた脳を再び回転させながら口を開いた。
「隣にも聞こえていたんですか…。あれは一体、何の戦いだったのでしょう?」
三笠が、ちょっとバツの悪そうな顔をしたため、神楽坂はあることに気付いた。
「あれ? でも三笠さん、確か隣のグループの司会やってましたよね?」
「まぁ…。神楽坂さんのほうばかりに耳を澄ませていたから…」
「意外です。三笠さんはそんなタイプではないと思っていました」
その後、神楽坂はさらに三笠の珍しい姿を見ることになる。

「神楽坂さん、申し訳ない。グループ分けのメンバーを見た時に、この可能性をちゃんと教えておくべきだったんだ。革新派の神楽坂さんと今日のメンバーは水に油だったからね。それに神楽坂さんに対抗意識を持っている人も多かったから…。ゴメン、今日のディスカッションが上手くいかなかったのは僕のミスだ!」
三笠らしくない雑な日本語。それに影響を受けたのだろうか。
神楽坂も珍しく早口の高音になった。
「いいえ、そんなことは…。いえ、そんなことより三笠さんって、結構喋れる人なんですね。今日はいい収穫がありました!」
神楽坂は、そう言って笑った。多分、三笠の前では初めて。
「っ…」
三笠にとっては、その笑顔が予想外過ぎて、完全に言葉を見失った。
実は、笑顔自体は見たことがあった。朝のTV画面で何度か。
しかし目の前の神楽坂はどうだ?
TVで見るよりずっと幼く、かわいらしいではないか。
-つづく-
神楽坂美咲との出会い 第二章
神楽坂のディスカッションにおける失敗を機に、教育係である三笠は、研究とは直接関係ない範囲についても広く話をするようになった。
「昨日、神楽坂さんの高校の時の論文、見させてもらったよ。ちょっとレベルが違うね。僕にはとても書けない。一体何者なの?」
「別に何者でもないです。ただ幼い時から色々な経験をさせてもらっただけです」
「ん…」
確かにゼミ室だけでなく、図書館、学食、帰り道と、二人が一緒にいる時間は長くなった。そして長くなるほど、神楽坂自身の学内とゼミ内での「立ち位置」は安定した。
余計な勧誘も理不尽な言いがかりも、大幅に減少したのだった。
しかし、二人の距離は一向に縮まらない。
元々、他人に関心がない二人だ。人と親しくなるための知識や経験に疎い。
社交辞令的な会話だけでは、お互いを知ったことにならないし、遠慮だらけでは深く踏み込めない。
「先日、三笠さんのネットに投稿された小説を読ませて頂きました。面白かったです」
「どうも…」
「はぃ…」
そう。会話が全く弾まないのが致命的だった。

実は…、周りの人間も、二人の「離れすぎ」には戸惑っていた。
あんなに一緒にいる二人だが、その体は触れるどころか、必要以上に距離を取り、神楽坂は三笠の横ではなく、常に半身後ろを歩くのだった。
ただ皆、そこを直接は聞きづらい。
そのため「二人が付き合っているのかいないのか…」、あちこちで賭けが発生した。
そして夏休みに入る直前、皆からの代表者が直接、三笠哲也へ真相を聞きに行った。
結果は…、「付き合っている」に賭けたほうが大損となった。

ある時…、正確には、二人の間で気まずい無言が続いてしまった時…。
神楽坂が意を決したように、ある提案をした。
「三笠さん、私達、面白いニックネームで呼び合いませんか? 自分のことも、もっと砕けた名称にして…。昔、親戚の子とやって楽しかった記憶があるんです」
三笠はしばらく逡巡した後、頷いた。
「そうだね…。まずはそこからお互いの固さを取っていくのもいいかもしれないね…」

1週間後。
学食でランチを食べながら、神楽坂が真剣な表情で三笠に話しかけた。
「昨日のゼミで、ぷーちゃんが発言された「地方過疎化における空間構造の変容」についてですけど、あたしゃー別の視点も推奨したいのですが…」
「そうだったの? それなら気を遣わず、皆の前で言ってくれて良かったんだよ。おいらはポン子の意見を凄く聞きたいんだから」
夏休みに入ったばかりで講義はなく、周りに殆ど人はいなかった。

1週間前に、二人で決めた約束事はこうだ。
まず、それぞれのイメージの「逆」で呼ぶこと。
そのギャップを楽しむと同時に、自らのイメージを背負うプレッシャーからの解放をも目指すものだった。
では、スタイリッシュで鋭く、繊細な三笠の真逆を表す言葉は何か?
神楽坂は時間をかけて考えた。
散々、取捨選択を繰り返した。
そして、最終的に推奨したのが「ぷー」だ。
確かにそこには緊張感のかけらもない。
それを聞いた三笠の第一声は、「言われたらムカつく」だった。
「そう言われないように頑張っている部分もあるし…」
ただ、すぐに首を傾げた。
「でも不思議だな。神楽坂さんに言われる分には、許せそうな気がする」

対して三笠は、神楽坂が周りから絶対に言われないであろう言葉を探していた。
おそらくこれまでの神楽坂にも、あだ名くらいはあったはずだ。
そのどれとも被らない、斬新な名前を…。
三笠が最終的に出した答えは「ポンコツ」だった。そしてそれを短くして「ポン子」にした。
それを聞いた神楽坂は、再びTVでは見せない、切なそうな表情を見せた。
三笠は少し不安になった。
神楽坂は小さく絞り出すような声を出した。
「私は自分にポンコツな部分があるのを知っています。でも小学生の頃からずっと、実際以上に評価されてきたのです」
「ごめん、なんかオレ、調子に乗った…」
「いえ、ありがとうございます! 今、三笠さんにそう呼ばれて、うん、何だろう…凄くホッとしたんです! 肩の荷が下りたんです!」
「あ、そうなの?」
三笠の眉が大きく垂れ下がった。
クールぶっている本人は、全く気付いていなかったが…。

次は、一人称を決める番だった。
「うーん…『おいら』はどうですか? 昔、親戚の「誠」って子がそう言っていて、凄くかわいかったので…」
「んーーー。人に聞かれない場所でなら言えるかな…。でも自分の殻を破るって結構、労力いるんだねー」
「では決まりです。私は自分のことを何と呼べばいいですか?」
「『あたしゃー』って言ってほしいです!」
「あたしゃー…」
「うん。去年のフィールドワークで山奥の村に行った時、おばあちゃん達が皆「あたしゃー」と言っていてね。なんかその温かい響きに感動した記憶があるんだ」
「分かりました。そうですね…、全く抵抗ないんで、あたしゃーどこででも言えますよーw」

こうして始まった新しいやり取り。
初めはぎこちなかった。特に三笠は下手くそだった。
それでも回数を重ねるごとにリラックスできて、次第に本音も出るようになってきた。

夏休みが明けた。
いつもの学食のいつもの席に、神楽坂が遅れてやってきた。
「ごめんなさい、ぷーちゃん…。ちょっと授業が長引きまして」
「全然大丈夫だよ。あ、ポン子はカルボナーラで良かった? おいら先に2つ頼んじゃったけど…」
「ありがとうございます。あたしゃーちょうどカルボナーラを食べたい気分だったんです」
「ねぇポン子…」
三笠が急に真剣な眼差しを見せた。
「はい?」
「ちょっとお願いがあるんだ」
「何でしょうか?」
「せめて二人きりの時は、敬語やめてくれないかな?」
このあたりから、二人の距離は急接近することになる。
-つづく-
神楽坂美咲との出会い 第三章
日本文化、中でも日本語の美しさを探している三笠哲也。
崎山ゼミに入った2年生の後期から、それを世間にも知ってもらいたいと強く考えるようになった。
【堅苦しい文献より、人目に触れやすいやり方を…】
先行モデルはない。
3年生になると、試行錯誤しながら、自ら、日本の美しさを取り入れた小説を書き始めたのだった。
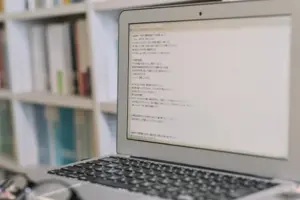
一方の神楽坂美咲は、過去と現在の日本文化を研究し、その先を予測しようとしていた。
革新的な手法に加え、ゼミ活動があくまで手段で目的が別にあることに、多くの先輩から反感を持たれた。
実際、現存する文化を破壊、否定するものと誤解され、非難を浴びることも多々あった。
それでも神楽坂のスタンスがブレることはなかった。
まるで未来を予測することが、自らの定められた運命であるかのように。

2010年10月9日。午前6時20分
三笠は、朝早くから車を運転していた。
助手席には神楽坂美咲が行儀よく座っている。
そしてスタバで買ったばかりのコーヒーの芳醇な香りが、二人を包み込むように漂っていた。
まだ先輩と後輩の関係の二人だが、傍から見れば、いよいよカップルにしか見えないのだろう。
学内では再び「二人が付き合っているかいないか」の「賭けパート2」が始まっていた。

出発地である横浜からは、結構な長丁場だった。
「疲れたら運転代わりますからね」
神楽坂の悪戯っぽい微笑みに、三笠は苦笑した。
「ポン子、免許持ってないじゃん…」
向かう先は、岐阜県の高山市。
そこで行われる「秋の高山祭」が、今回、二人だけに共通するフィールドワークだったのだ。
16世紀後半が起源とされる高山祭りは、「日本三大美祭」の1つとなる。
その祭屋台に施された昔ながらの彫刻や刺繍、そして何より「精巧なからくり人形」を見るのが二人の目的だった。

車は順調に進んでいたが、途中の山道で、狸らしき何かがいきなり飛び出してきた。
「危ないっ!」 「キャーーッ!」
急ブレーキと同時に、三笠の左手が神楽坂の右肩前を強く抑えた。
タイヤの悲鳴のような摩擦音と上半身の痛みが、神楽坂の恐怖を駆り立てる。
車はスライドしながらも、何とか止まった。
幸い、三笠の強い力のおかげで、神楽坂の上半身も前方に飛び出すことなくシートに留められた。
「大丈夫!?」
息の乱れた三笠が心配そうに声をかけた。
「うん。怖かったけど…、ありがとう。おかげさまで大丈夫だった…」
「ふーーーっ、それは本当に良かった…」
髪の乱れた三笠が胸を撫で下ろした。

神楽坂は、三笠の新たな一面を見た思いだった。
三笠は、計算された動きをするタイプだった。歌舞伎や日本舞踊のように、頭の先からつま先まで、常に統制された美しさを表現する。
ところが今の混乱っぷりはどうだ?
三笠らしくない慌て方と動揺だった。
やはりフィールドワークは大切だと神楽坂は実感した。学内という安全な場所だけでなく、外に出てみて初めて分かることもある。
正直、学内で女性達からキャーキャー言われている三笠の魅力は理解できなかった。
しかし今のドタバタな三笠には、逆に好感を持つことができた。
何より、自分を大切にしてくれていることが知れて、言葉では言い表せないほど嬉しかった。

11時40分。
車は岐阜市内に入ったが、まだ少し時間に余裕があるということで、「お好み焼き屋さん」に寄ることにした。
「はい。お嬢さんのおっしゃる通り、このあたりはどこも岐阜風でやっていますよ」
店主のこの言葉に神楽坂は頷くと、かなり薄く生地を広げ始めた。
そして生地の上にキャベツとネギ、続いて天かすを手際よくのせていった。

呆気にとられる三笠。それに構わず神楽坂は、手を動かしながら尋ねた。
「ぷーちゃん、紅しょうがって大丈夫?」
「うん、入れてもらって大丈夫」
神楽坂は、紅しょうがを加えた後、両面を焼きながらお好みソースをかけ始めた。
三笠はいよいよ素朴な疑問を口にした。
「ポン子…、何でできるの?」
「え? 地方の食文化も立派なフィールドワークでしょ?」
「なるほど…事前に勉強していたのか。さすがだなぁ…」
「ウソウソ、たまたま親戚がこっちにいて、昔、作ったことがあるの」
神楽坂はそう笑いながら、器用にお好み焼きを三つ折りに畳み、もう一度、お好みソースをかけた。
関東とはまるで違う。三笠にとっては初めて見る形だった。

三笠は、ただただ出来上がるのを見つめるだけだったが、心の内には複雑な感情が芽生えていた。
それは2つ年下の神楽坂へ抱く初めての感情だった。
「母性」
多分、その感覚が一番近い。
まるで自分は、「一般的なお母さん」に料理を作ってもらうのをじっと待つ、「一般的な子供」のようだった。
そして何だろう?
神楽坂がゼミに入ってきてから、ずっと教育係として守ってきたつもりでいた。しかし今は、逆に守られている安心感がある。
「あぁ、いい匂い! ぷーちゃん、どうぞ召し上がれっ」
「ありがと…ぅ」
神楽坂の屈託のない優しい笑顔がまぶしい。
三笠はついに我慢できず、俯いてしまった。
【オレはずっと問題のある家庭で育ってきた…。ずっと辛かった…。これが母の温もりなのか?】
鼻の奥がツーンとしてきた。
涙が零れ落ちそうになるのを必死でこらえながら、三笠は黄金に光り輝くお好み焼きに手を伸ばした。

13時50分。
高山祭の会場へは無事に到着したが、想像以上の観客で溢れていた。
三笠はともかく、神楽坂は、前の人の背中と頭しか見えない状況だった。
「どうする?」
2人は相談した後、少し祭屋台から離れてしまうも、人の少ない高台のほうへと移動した。
祭りはまさに素晴らしいものだった。
この光景を400年前の人達も見ていたと思うと感慨深い。
そんな中、からくり人形の巧妙な動きをもっと見ようと神楽坂が身を乗り出した。
が…、足場が不安定な箇所だ。バランスを崩して倒れそうになった。
気付いた三笠が咄嗟に両手を出し、後ろから抱きかかえた。
「ごめん…ありがとう」
しかし三笠は、そのバックハグした両手を離そうとはしなかった。
離さないどころか、さらに強く抱きしめていき、二人の密着度は、出会ってから初めてマックスに達した。

呼吸もできなくなるほど、神楽坂の背中に強く押し付けていた自分の顔。
三笠はそれを少しずつ、だが一瞬たりとも離れぬように強く擦らせながら、神楽坂のうなじへと登らせていった。
神楽坂は、微動だにせず黙りこくっている。
三笠の顔が、神楽坂の右耳に到達した。そして囁いた。
「オレは、こんな風に二人で美しいものを、もっともっと見に行きたいんだ。正式に付き合ってくれないか?」
しばらくの時間が経った。
二人とも動かないのは、ずっとこのままでいたい衝動だったのかもしれない。
先に動いたのは、神楽坂のほうだ。
三笠の手をゆっくりと振り解いた。
そして長い黒髪を整えながら振り向くと、赤らめた顔を三笠の正面に据えて笑った。
「私でよければ喜んで」

神楽坂の潤んだ瞳を見た三笠は、もう溢れ出す「想い」を抑えることができなかった。
目の前にある笑顔を、壊れないよう自分の両掌で優しく包み込んだ。
そして自分の唇を、ゆっくりと神楽坂の唇へと近づけていった。
耳には大音量の祭囃子が鳴り響いている。何とも非日常な世界だ。
唇をさらに近づけていった。
神楽坂の両腕が動き、自分の背中を優しく包み込んだのが分かった。
あぁ、許されたのだ。
あぁ、この満たされた幸福感。
二人の唇が触れた瞬間、世界中の全ての音が止まったように三笠哲也は感じた。
-f i n-

 毛利悠介
毛利悠介ワンダフォー! ひゅーひゅー!



さすがネッキャン。二人とも恥ずかしいでしょうに、よくぞ公開してくれたわ!



これほど素敵に結ばれた二人が今は…。ブルッ…



ホントに清明くんは黙っていた方がいいよ
恋のマジック
三連休が明けたばかりの2010年10月12日。
帝香山大学では、朝から大きな衝撃が走っていた。
学内1のイケメン三笠哲也と皆のマドンナ神楽坂美咲。
2人における距離感が、尋常ではなく近付いていたからだ。


確かに以前から噂にはなっていた。
しかしここまで堂々とイチャイチャされると、4日前までとのギャップに戸惑ってしまう。
一体、この連休中、2人に何があったのだろう!?
崎山ゼミのメンバーも、三笠と神楽坂のラブラブぶりには驚いた。
「ミサ…」
「哲也くん…」
呼び合う2人の言葉尻には、何人たりとも入り込めない💛マークがハッキリ見てとれた。
もう学内にいる誰もが認めざるを得なかったのだ。
2人が完全に恋人となったことを。


1か月が過ぎても三笠と神楽坂のラブラブぶりは変わらなかった。
そうなるともう、校庭の木と同じになる。
まるで昔からそうであったかのように、日常の風景となるのだ。
それでも時々は、諦めきれない女性が三笠を誘うこともあった。
「三笠くーん、この後、ご飯食べに行かなーい?」
三笠はその度に素っ気なく謝った。
「ごめん。約束があるんだ」
そして次の瞬間には、満面の笑みを浮かべて美咲に手を差し出すのだった。
「行こう!ミサ」
無愛想だった三笠に、そんな笑顔ができるなんて誰も思っていなかった。


そのため、一部の女性達は「NEW笑顔が見れるようになっただけ、神楽坂には感謝するかぁー」と慰め合った。
そこからも、2人のラブエピソードには事欠かない。
学内の誰もが何度も目撃することになる。
さっき神楽坂が少し寒そうな素振りを見せたんだ。
そしたら哲也がすぐに自分のジャケットを脱いで彼女にかけたんだよ。
神楽坂が「大丈夫だよ、平気だから」と言った後、哲也は何て言ったと思う?
にっこり笑って「いや、心配だから俺のために着てくれ…」って…。
クソーっ、俺もイケメンに生まれたかったー!



ねぇ美咲。三笠くんって家でも優しいの?



はい。私、哲也くんがいてくれて本当に幸せなんです



そうなんだぁ。内ずらも外ずらも変わらない男って本当にいるんだねー



いいなぁ、哲也は神楽坂の料理が食べられてー



あぁ、ミサの料理は本当においしいんだよ



一番好きな料理は何?



どれも好きだけど、彼女の笑顔が一番好き…かな



そうかぁ、哲也は人間らしくなってホント良かったよ



2人は本当に仲がいいね



あぁミサのおかげで毎日が楽しいんだ。感謝してもしきれないほどだよ



こちらこそ毎日、哲也くんの存在に感謝しているんです



それは何より。いつまでもお幸せにね!
正直、2人が付き合い始めた当初は、周囲からの嫉妬や妬みがあったのも事実だ。
しかし、いつしか2人の愛情溢れる言動に心を動かされるようになり、今や皆のお手本となっていた。
「自分達もあのような恋愛をしてみたいっ!」と。


珍しく関東を直撃する台風が近付いている日のことだった。
時刻は朝の6時半。
TVで外の様子をライブ中継している中、スタジオにいるキャスターが呼びかけた。
「神楽坂さーん、今よろけましたけど大丈夫ですかぁー?」
「はい!あたしゃー大丈夫でーす!」


キャスター2人は一瞬顔を見合わせた。が、すぐに1人がフォローに回った。
「どうやら口が上手く回らないほど風が強いようですね。以上、お天気コーナーでした!」
それを自室で画面越しに見ていた三笠の口元が少しだけ緩んだ。
そしてすぐに立ち上がると、車のキーを取り上げた。
1時間後。
三笠はTV局まで美咲を迎えに行っていた。
「ありがとう哲也くん!」
スマホで駐車場所を知らされていた美咲は、喜んで車の助手席に乗り込んできた。
「強風の中のレポートご苦労さま。呂律が回っていないようだったから心配していたんだよw」
「もう、意地悪ねー! あたしゃー咄嗟に出ちまったんだよ~」
「ごめんごめん。とてもかわいかったよ。あとカフェで温かいコーヒー買ってきたから」
「わぁ、ありがと!」
「あと1つ朗報。今日、休校だって!」
「わーーっ! 嬉し過ぎる! じゃあここから完全にフリーなのね!」


2人はそこから、思い切りデートを楽しむこととなった。
デート中は、テンション高くはしゃいでいた美咲。
TVや大学とも異なるその表情を、三笠はずっと見つめていた。
それに気付いた美咲が少し心配そうな目をした。
「え? どうしたの? 私、化粧落ちてて変?」
「ううん。TVより今のミサのほうがずっとかわいいよ。このまま俺だけのミサでいてくれたらどんなに幸せか…」
「えぇ、ずっと一緒ですよ~」
そう微笑んで美咲は、三笠の手を強く握った。


20時50分
楽しかったデートもいよいよ終わりとなる。
美咲の家の門限は21時であるため、車はすでに自宅前に横付けしてあった。
車内には寂しさと切なさが入り混じっており、2人の会話も劇的に減っていた。
いよいよ車を降りねばならなくなった美咲は、ドアーに手をかけながら尋ねた。
「ねぇ、明日は台風が通り過ぎちゃうから…、局に迎えに来てくれないの?」
その少し上目遣いの表情を見て、三笠はたまらない気持ちになった。
美咲の左腕を掴むと自分の方へ引き寄せ、抱きしめながら囁いた。
「これからは毎朝迎えに行くよ。それで一緒に通学しよう…」
美咲も小さく囁いた。
「ありがとう…愛してます…」


三笠が卒業するまでの1年半、学内では誰もが羨む公認のカップルだった。
三笠自身もよーく分かっていた。
2人共、初めて異性と付き合って、完全に舞い上がっている状態であることを。
そして後も先もない。
今、自分の限りある人生で一番幸福な時間を過ごしていることも。
-f i n-



この時期、僕も2人に会っていますよ♪。クールな哲にぃがミーちゃんにだけデレデレだったのも懐かしいですねw



思い返すと恥ずかしい部分もあるでしょうが、こんな素晴らしい幸福感を味わえたのは、人生の大きな財産ですね!



なるほど。この時点でもう財産を手にしているのか…
21歳当時の三笠の詩
最近付き合い始めた、まだ未熟な若いペアがいた。
恋に燃える2人は、毎日、こんなに幸せでいいのかと泣き、これほど愛し合っているのに、いずれ別れなくてはならない日が来るのかと泣いた。


そんな2人が旅行先に選んだのは、誰もいない無人島だった。
2人だけの世界を永遠に感じたかったからであり、世の理(ことわり)から逃げるためだった。
無人島の朝。
日の出と共に生命の誕生を感じることができた。
昼の輝く強い日差しには、人生の充実とピークを感じた。
2人は貪るように歩き、泳ぎ、人生を謳歌した。


しかし、次第に太陽は沈み、寂しい気持ちが二人を襲い始めた。
そう。ここからがこの旅の本番なのだ。
何度も、「太陽よ戻れ!」と叫んだり祈ったり儀式を行った。
あらゆる努力をした。
努力をしてみたが太陽が戻るはずもなく、無情にも日は沈んだ。
あんなに楽しかった一日が終わるのだ。


いよいよ2人は肩を寄せ合って泣いた。
やはり運命には逆らえないのだと。
こんなに愛し合っているのに、いつか死がやってきて2人を必ず分かつのだと。


夜の暗闇の中、泣き疲れた2人はいつしか眠ってしまった。
それが小さな死だとは分かっていたのに。
翌朝、太陽は再び登った。
2人で黙ってそれを眺め続けた。
やはり生命の息吹を感じた。
日は沈んでもまた登るのだ。
たとえその時、どちらかが、もしくは2人共いなくなっていても…。


2人は少しだけ悟った。
すでに2人は、昨日までの自分達とは少し異なる、新しい生命体であることに気付いたのだった。
その日の夕方、2人は島を出た。
2人の幸せは、島に来る前とは、少しだけ変わっていた。
-f i n-



あーかなり誇張してあるけど、まだ青い恋愛感情がピークの頃の私達の話だと思うわ。あー恥ずかしっ



三笠さんはホントに神楽坂さんのことが大好きなんですねっ!



ここまで人を好きになれる2人が凄いっス

