メンバーエピソード
神足悠香(幼少期)
Next Nex
登場人物
神足悠香
(幼少期)

【私は、兄に何一つ勝てていない】
神足悠香は、物心ついた頃からそう感じていた。
悪い意味ではない。
2つ上の兄、神足晃は、自分が生まれる前から優秀なのだから、自然なことだった。
「悠香ちゃんのお兄ちゃんってホント凄いねー」
そう。妹としては誇らしくもあった。
両親も、晃と比較することなく、悠香の意見を尊重し、良きほうへ導いてくれた。
だからこそ劣等感など生まれるはずはなく、兄との関係も良好で尊敬もしていたのだった。
少なくとも7歳までは。

悠香の心に「さざ波」が起こり始めたのは、小学2年生になってからだった。
「悠香ちゃんの家って有名なんだねー」
父親が、誰もが知る大企業の2代目社長で、兄がその跡を継ぐべく英才教育を受けている事実。
それを知った時、自分の「負け」は必然だったのだと強く感じた。
【もし、私が年上だったら、どうなったのだろう?】
【もし、私が男に生まれていたら、こうはならなかったのではないか?】
クラスメイトからの羨望の眼差しとは裏腹に、悠香には疑念が膨らんできた。
【跡継ぎでない自分など、最初から兄と比べられていない?】
【自分の意見が通ってきたのは、どうでもよい存在だったから?】
元々が、負けず嫌いな性格だ。
両親や兄を嫌いになることはなかったが、少しはギャフンと言わせたくなってきた。
勝手に決められた運命に負けたくなかった。
そこから悠香は、兄に勝るものを必死で探し始めた。
【何か一つでもいいから!】

運動、勉強、礼儀作法、人付き合い、乗馬、ヴァイオリン。
晃と対決できる全てにおいて、何をどうがんばっても勝てなかった。
ムキになる悠香へ母親は「2つも歳の差があるのですから仕方ありませんよ…」と慰めた。
しかし、悠香が比べていたのは、常に同じ年齢だった時の晃だった。
しつこいくらい、先生やコーチや師範に尋ねていった。鼻息荒く。
「お兄ちゃんが私くらいの時はどうだった?!」
結果は聞くまでもない。
晃は、生まれ落ちた次の瞬間から、厳しいエリート教育を施されているのだ。
両親に甘やかされ、自分の好きなことしかやってこなかった悠香に勝てる余地はなかった。
.webp)
悠香が小学4年生になった初夏のことだった。
乗馬教室の帰り道、お腹が空いたということで、晃とコンビニに寄った。
珍しくコーチに褒められて、機嫌が良かったからだろうか。
入店時に流れた音を何気なく「ファレラレミラー♪ミファミラレー♪」と繰り返した。
「何それ?!」
隣にいた晃が目を丸くして尋ねた。
「今流れたから…」
「そうじゃなくて、ユウは何の音か分かるの?」
「え? 分かるでしょ? いつもドレミの音で聞こえてない? 救急車の音とかも」
ゴクリと喉を鳴らせて晃が尋ねた。
「…救急車って、何て言ってるの?」
「シーソーシーソーじゃん」
「凄っ…」
悠香は、この時の晃の表情を決して忘れることはないだろう。
後にも先にもこの1度だけだった。
まるで神にひれ伏すかのような畏敬の念を、その眉と目と口で表したのだった。

「絶対音感」
音名を瞬時に正確に判別できる能力のことで、人口の1%未満しか持っていないと言われている。
そして誰も気付けていなかったが、悠香には生まれつき、絶対音感が備わっていた。
悠香自身、晃に指摘された時には驚いた。
皆、普通に音の高さを聞き分けられるものだと思っていたからだ。
音名とは、いわゆる「ドレミファソラシド」となる。
つまり悠香は、日常生活で入ってくる音が全て「ドレミファソラシド」のいずれかの音階で聞こえていたのだ。

どんな能力でもメリットとデメリットは存在する。
絶対音感のメリットは、当然ながら音楽関連に有利な点だ。
音楽の成績は常に良かったし、練習しなくても歌やピアノを上手にこなせた。
デメリットは…、おそらく一般の人にとっては想像もつかない点となる。
雑音ですら音名に変換してしまう煩わしさはまだしも、音名と違う言葉が耳に入ってくることで、脳が強いストレスを受けるのだ。
具体的には、「ド」という言葉なら「ド」の音階であってほしかった。
「レ」と発しているのに「レ」の音階でない時に、その違和感に耐えられなくなるのだった。
例えば、有名なドーナツ屋さんのCMソング。
「〇スター〇ーナツ♪」
【これ、音名で言うと、正確には、レスターミーナツ♪、だからーっ!】
最悪なのは、ドレミの歌だった。
音階の歌のクセに、最後の裏切りが非道すぎる。
「ドーはドーナツーのドー♪」
【これ、最後はドじゃなくてミになっているからーっ!】
「レーはレモンのレー♪」
【これ、最後はレじゃなくてファだからーっ!】
悠香の心の絶叫は、延々と続くこととなる。

いずれにせよ、初めて兄に勝てるものを見つけられた悠香。
見つけた翌日には、早速、晃をカラオケに誘い、満点を取って完勝した。
何度、挑戦されても完勝した。
晃は「凄い才能だよ。今すぐ新藤さんの事務所に入って歌手を目指そうよ!」と嬉しそうに笑った。
悠香自身、自分がやっていく道はこれだと確信し、母親に頼み込んでボイストレーニングとダンス教室に通わせてもらうことになった。
好きで得意分野の習い事だ。
週1回が週2回に、そして週3回と、どんどんノメり込んでいった。
中学生になった頃には、トレーナーから絶賛される回数も増えたが、自分のレベルがどれくらいなのかは分からなかった。
他人と競争するためにやっているわけではなかったし、歌もダンスも個人レッスンだったのだ。
一緒にやっている仲間がいないので、比べる対象がなかった。

悠香が高校2年生になった。
そのタイミングで、晃はアメリカの大学に進んだ。
「ちょっとMBA(Master of Business Administration)を取ってくるよ」
軽い口調で晃は笑ったが、悠香に無理なレベルであることは、自分が一番よく分かっていた。
跡継ぎとしての晃のステップアップは順調で、家族は何も心配していなかった。
だからこそ両親は、悠香にはいい意味で無関心で、何でも好きなことをさせてくれた。
「俺が帰ってくる頃には、ユウは歌手になっているのかな?」
「はぁ? なれるわけないでしょ。リリーちゃんじゃあるまいし。普通に大学生よ。まぁ本気出してMOSくらいは取っているかもねー」
「おーMOSか、懐かしい。オレ、確か中学の時に取ったようなw」
「うるさい! とっととアメリカ行け!」
「おぅ。悪いけど、父さんと母さんをよろしく頼むな」
おそらくこの会話の後からだった。
悠香が自分の将来を少しずつ考えるようになったのは。

【兄が帰ってくる時、私は何者になっているのだろう?】
何度も自分に問いかけたが、答えは出なかった。
会社の業績は堅調で次期社長も優秀。
神足家自体も、2代先まで遊んで暮らせるだけの資産を持っている。
いい意味でも悪い意味でも、悠香にはやるべきことがなかった。がんばる必要がなかった。
ゲームで言えば、もうゴールしているので、正直、ここからの余生が退屈なのだ。
学校での進路相談も、先生とお互いやる気を感じられない会話が交わされる。
「まぁ神足さんなら、どうにでもなるわね」
毎回、それが結論になった。

悠香が高3の夏休み。
推しの歌手が出ているライブハウスに行った時のことだった。
インフォメーションコーナーに「地下プロデューサーX氏、仮面アイドルグループNexを結成か!?」とのニュースが貼り出されていることに気付いた。
【仮面アイドルグループって?!】
聞きなれない言葉に、突っ込まざるを得なかった。
その一方で、顔出ししないアイドルに需要があるのか興味も湧いた。
運営の作戦に乗ってしまうのはシャクだが、携帯をかざしてQRコードを読み込んだ。
これが運命の分岐点であることには、まだ気付いていなかった。

「Nex」
携帯に映し出されたページを閲覧していったが、どうも様子がおかしい。
仮面アイドルグループについての詳細は書かれておらず、メンバーも存在していないニュアンスだった。
悠香は、当初の目的とは別の地点へ吸い込まれていきそうな怖さを感じていた。
【もしかすると、メンバー募集のページなのだろうか?】
悠香のスクロールの手が止まった。
「第一次オーディション。挑戦者受付中!」
「自分の才能を生かすチャンスだ!その限りない才能を見せつけよう」
その文面を見て、心が少しずつ湧きたっていくのを感じていた。
まるで自分のために用意されたイベントのような気がしてきたのだ。
ゲームで言うなら、全く新しいゲームをゼロから始められる予感だった。

悠香の頭は、ページを眺めながらも様々な計算を始めていた。
「仮面アイドルNex 挑戦者募集! 来るならコイや!」
何度見ても、この文言が「負けず嫌い魂」に火をつける!
オーディションを受ければ、今の自分の歌とダンスのレベルを知ることができる◎
ずっと1人きりだったので、仲間と一緒にパフォーマンスをしてみたい
デビューしたとしても、仮面をつけているので、家族に迷惑をかけずに済む

しかし…、さすがにボタンを押して先に進むのはためらう。
生半可な才能で目指せる世界ではないし、好きだけでやれる仕事でもないし、独断で決めていいとも思えない。
【一度、冷静になろう…】
そっとページを閉じようとした直後、兄、晃の声が頭の中に鳴り響いた。
「俺が帰ってくる頃には、ユウは歌手になっているかな?」
1年前は、からかわれているのだと思った。
しかし、今思い返すと明らかに響きが違う。
「ユウの絶対音感を、うまく活かせよ…」
今更ながら、そういう意味だったのだと悟った。
そして何で忘れていたのだろう?
【私にはこの道しかない!】
そう小学4年生の初夏に誓ったはずだ。
悠香は人差し指を再び動かした。兄が背中を押してくれている。
もう迷いはしない。
力強く「挑戦する」ボタンを押した。
-f i n-
 佐々木拓海
佐々木拓海悠香ちゃんの家ってそんなに凄かったんだ。なのに何で僕の隣でバイトしてんの? ハッ、まさか僕のこと…



よくできた兄と自由奔放な妹か。世の中には色々な兄妹の形があるものだ



Nexほど個人を見分けられないグループってないよね。どれが悠香なのか全く分からないよ!
裕木清明(28歳当時)
引き継いだ十字架
登場人物
裕木清明
(28歳当時)


1984年6月23日。
まだ昭和と呼ばれていた時代だ。
裕木錬太郎(23歳)は、目を開けたら人を殺していた。
果たして、そんなことがあり得るのだろうか?
誰がその現実を信じられるだろう?
気付いたら自分が殺人者になっていたのだ。


錬太郎が病院のベットでその事実を知らされた時は、皆が示し合わせて自分を騙しているのだと思った。いや、頼むからそうあってくれと願った。
しかし、自分の記憶に無くても事実は進行していた。
医者によれば、持病である1型糖尿病が関係しているとのことだった。
車の運転中に極度の低血糖症を起こして気を失い、人をはねていたのだ。
そう知らされても頭の整理はつかない。受け入れたくもない。
「夢なら覚めてくれ」
その感覚をエンドレスで味わっていた。


錬太郎の周りには、泣きじゃくる母親だけでなく、医療関係者や警察関係者など大勢の人間がいた。
自分も本当は泣き叫びたいし、1人にしてほしいのだが、社会はそれを許してくれなかった。
警察の話によれば、亡くなったのは、大学3年生。
前途洋々たる青年だったそうだ。
それを聞いた時、いよいよリアルと向き合わなくてはいけない覚悟が生まれた。


錬太郎は病院を退院すると、警察官が付き添う中、青年の両親のもとへ謝罪に行った。
しかし何せ、記憶がないのだから身に覚えがない。
実感が伴わないことをどう謝罪できるのか自分でも分からなかった。
それでも青年の両親の顔、希望の光のない目を見た瞬間に、途方もない罪の重さを感じた。
自分は取り返しのつかないことをしてしまったのだと。
どんな言葉を絞り出したかは覚えていない。
ただただ精一杯、頭を下げ、今後自分ができることと、お墓参りも欠かさず行かせて頂くお願いをした。


謝罪が終ると、ずっと黙って聞いていた青年の父親が口を開いた。
「私達は辛すぎるので、もうあなたとはお会いしたくありません。お墓参りも結構です。あなたも、私達や息子のことは忘れてもらって結構です。多分、息子もあなたに十字架は背負わせたくないでしょう。皆、不幸になりましたが、この先も皆で不幸になることはないと思うのです」
「いえ、そんな…」
錬太郎の言葉をさえぎるように、今度は青年の母親が口を開いた。
「あなたの謝罪は今、十分受けました。私達があなたを許せるかは分かりませんが、あなたはもう自由です。これからもこの社会で存分に羽ばたいてください。そして息子の分まで幸せな人生を生きて下さい」
「ワーっ!ワーッ!」
感情の処理が追いつかず、堰を切った獣のような大声が繰り返された。
その後、号泣し続ける錬太郎を、二人の警察官が抱きかかえながら退出した。


2年後。
錬太郎は完全なる社会復帰を果たした。
早期に示談が成立していたことと、青年の両親の働きかけで実刑は免れ、執行猶予で済んでいたからだった。
様々な葛藤があったが、悔いるだけの人生は送るまいと決めていた。
幸せに生きるかは二の次で、あの家族に恥じない、できれば社会に貢献できる人生を送りたかった。
錬太郎は、できる限りの努力は続けた。
それでも総理大臣にはなれなかった。
会社の社長にもなれなかった。
画家にも歌手にも俳優にも、スポーツ選手にも小説家にも研究者にもなれなかった。
このままではいけない。
前途洋々だった若者に、これでは顔向けできないと焦燥の念にかられていた。


そんな錬太郎ができたこと、結果として行ったことは、計画的な離婚を3回繰り返して、子供を8人作ることだった。
3人の奥さんには全て事情を話し、納得してもらった上で、結婚と離婚の協力をしてもらった。
そして必死で働いた。とにかく馬車馬のように必死で働き続けることしかできなかったのだ。
そのお金で、8人の子供達にたくさんの投資をした。教育にできるだけお金をかけた。
錬太郎に趣味はなく、遊びもせず、無駄遣いもせず、情熱を子育てのみに傾けた。
ただひたすら、3人の元奥さんと8人の子供達に愛情を注ぎ続けた。


8人の子供達は、興味を示すものは殆ど体験できた。勉強も運動も芸術も遊びも全て。
その中でそれぞれの長所を伸ばし、すくすくと成長していった。
子供達は、父親とたくさん会えない寂しさはあったろうが、総じて幸せだったのではなかろうか。
特に不満を口にすることもなかった。
では、廉太郎はどうだ?
彼の人生をどう評価すればいいのだろう?
廉太郎は、幸せだったのだろうか?
がむしゃらに生きた命は、58歳という若さで燃え尽きた。
多分、全てを出し切ったのだ。
3人の元妻達は、「家族に愛情を注いでいる時が一番幸せそうだった」と口を揃えた。


廉太郎は死の直前、8人の子供達を集めていた。
自らの35年前の過ちを伝えていた。
その後、涙を流しながら我が子達に懇願したのだった。
「どんな形でもいいから、社会に役立つ仕事を…」
「父さんが受けた恩を返すような活動を…」
「無能な父さんができなかった分、少しでもいいからしてくれ」と。


裕木清明が、父親のこの遺言を聞いた時は28歳だった。
すでに、いい大学を卒業し、いい会社にも就職して、生活は安定していた。
しかしまだ、父親が望むことは、何一つできていなかったことを思い知らされた。
命を削ってまで自分を愛してくれた父親の遺志は尊重したい。
しかし具体的に、一体何をすればいいのだろう?
他の異母兄弟とも話したが、明確な道は見えてこなかった。


モヤモヤを抱えながら3年が経った。
母親からは、「今のままでもお父さんは喜んでいると思うよ」と言われていた。
そんなある日、行きつけのお弁当屋さん「Bサイン」で、ネットキャンバスというサークルの存在を知った。
「we help us each other」
そのキャッチフレーズが、心のどこかに引っ掛かった。
管理人である斎藤千歳に頼み込み、オブザーバーという安全な距離を保った上で、参加させてもらうことにした。
自分が何をできるのか?
これから何をすべきなのか?
それはまだ分からないが、当面は、この流れに乗ってみようと考えていた。
この場所にいれば、いずれ見えてくる予感がしていた。
流れ? 予感?
何とも不思議なことだ。
非科学的なことを一切信じない裕木清明にしては、極めて珍しいことだった。


-f i n-





なかなか衝撃的な話です…。
きっと優しいお父さんだったのでしょうね



そんなに難しい話じゃないような…。流れにのったのだから、後は動けばいいだけだと思いますけど。そんな遠くから眺めていないで…



お前は本当にリスクを負わない男だな。そこまでいくと清々しいわ
伊藤明日香(21歳当時)
獅子王丸から伊藤明日香へ
登場人物
伊藤明日香
(21歳当時)


2013年7月15日。
伊藤、お前は礼儀正しくて優秀で、まだ警察官として日が浅いのに、考え方もしっかりしている。
そんなお前だからこそ、伝えておきたいことがある。


私のキャリア20年の中で、いまだ品があって礼儀正しい犯罪者を見たことがない。所作が美しい犯罪者も見たことがない。
それら気品を備えた者がいるならば、もはや犯罪のレベルでは括れない気がしている。
おそらく犯罪者本人も、それが罪とは思ってないだろう。
そう。美しい理念すら携えた犯罪者予備軍は、世を変えうる可能性を持った「革命家」と呼ぶべきなのかもしれない。


実際、犯罪者と革命家は紙一重のところにいる。成功すれば革命家、失敗すれば犯罪者。
ジョージ・ワシントンは、勝ったから初代アメリカ合衆国大統領だが、負ければただの戦争犯罪者で、名前さえ知られることはなかった。
日本においても、226事件を起こした青年将校について詳しく知っている人は少ないだろう。失敗したからだ。


もちろん現行を維持したい社会のトップは、理念があろうとなかろうと、革命を絶対に許さない。
現社会にとっては犯罪でしかないので、全力で阻止するはずだ。
だから伊藤、これは警察官の中でも、お前だけにしか言えない。
仮にそんな礼儀正しく気品溢れる犯罪者予備軍に出会ったら、偏見を持たず役割にも囚われず、全力で人として向き合え。
そして見極めろ。
同類のお前なら…、鏡の中にいるお前なら分かるかもしれない。
本当に正しいのはどちらなのか?
お前はどちらにつくべきなのか?
現社会なのか、その人間なのか。
-f i n-



歴史の教科書って、勝った側に都合のいい解釈の積み重ねですからね…



そうなんスか!僕はそんな歴史、学びたくないっス!



拓海は勉強したくないだけだろーーっ!
伊藤明日香の過去
登場人物
伊藤明日香
(小学生当時)





明日香さんへの取材を終え、掲載の許可も頂きました。しかし壮絶過ぎるので、エピソード化は難しく、私と三笠さんの判断で、最小限の情報だけ紹介させて頂きます
伊藤明日香が小学3年生の頃、両親が経営していたコンビニで、少年達4人が万引きをする。
父親が追いかけたところ、1人の少年が国道に飛び出し、不幸にも車にひかれて亡くなった。


世間は少年を殺したとして父親を責めた。
凄まじい誹謗中傷がやむことはなく、コンビニはすぐに潰れる。
直後に父親は自殺。
生活に困った母親と一緒に、親戚達にお金を借りに行くが、どこも貸してくれず。それどころか世間体を気にして「二度と顔を出すな!」と縁を切られる。
母親はその後、精神病院へ入院し、一年後に死亡。
身寄りが無くなった明日香は、弟と一緒に施設に入所。
半年後、弟が突然、消息不明となる。
警察も形ばかりの捜索で見つからず、未だ弟とは再会できていない。


家族が次々といなくなり、天涯孤独へ。
幸せだった生活が一気に地獄へ。
人間の悪意を嫌というほど見せつけられ、日々、明日香の中にとてつもない量の復讐心が蓄積されていった。
【絶対にこの世を、この世の人間達を許さない!】
その思いだけを胸に、明日香は成人した。
まだ犯罪者になっていないのは、ある意味、奇跡とも言えた。
-f i n-



これは…かける言葉が難しいわ



俺は明日香シスを手助けするぜ!



とにかく明日香さんが心穏やかに過ごせるよう、お手伝いさせて下さい
津雲大輔(幼少期)
悪への転身(前編)
登場人物
津雲大輔
(幼少期)


津雲大輔は、幼い頃から「正義」に憧れていた。
ヒーロー漫画を見過ぎた影響もあったのだろう。
「悪は必ず撲滅する!」
小学生の頃は、それが口癖だった。
そして…、将来は絶対にウルトラマンになると信じていた。
だからこそ、なれないことを完全に悟った中学生の時はショックだった。
それでも何とか頭を切り替え、22歳の春に、親友である泉獅子王丸と共に「法の番人」である警察の門を叩いたのだった。
しかし、わずか2年だ。警察官の職を放り捨てるまで。
あれほど正義感に溢れていた津雲が辞めることになったきっかけはいくつもある。
それはまるで、十人十色の運命の女神が、次々と津雲をいざなったかのようだった。


津雲を変えた運命の1つとして、E木S吾との出会いを避けては通れない。
E木は、警察内部では「昭和最後の大物ヤクザ」と位置付けられ、身内からは「会長」と呼ばれていた。
年齢は80を超えていたが、新人の津雲にもきちんと敬語を使える器の広い人物だった。
津雲がE木の組員を捕まえるたびに、家宅捜索を行うたびに、2人はよく話をした。
暴力団対策法。
津雲が警察官になる5年前の、1992年3月に施行された法律だ。
そしてイケイケだった津雲は「暴対法の申し子」として、ヤクザ社会から恐れられた。


「津雲さん、あなたみたいに熱心な人と出会えたことは嬉しいですが、頑張って頑張って社会は良くなりましたか?」
E木の微笑みながらの問いかけに、津雲は毅然と答えた。
「俺はそう信じている」
「それは何よりです。ところで津雲さんはアメリカの禁酒法を知っていますか?」
「あぁ、1920年にできたアルコールの製造や販売、輸送、輸出入を禁止する法律だな」
「では、その結末も知っていますか?」
「確か、ブラックマーケットに粗悪なアルコールが出回って死者が続出し、ギャングによる密造と販売が横行して治安がさらに悪くなったと言われているな」
「今はその状況に似ているとは思いませんか?」
「思わないね。そもそも禁酒法は欠陥だらけの悪法だった。対して暴対法は様々な角度から検証された素晴らしい法律だ。俺はこの法律を守る番人になれていることを誇りに思っている」
「なるほど…。少し質問させて頂いてもよろしいですか?」
「さっきから質問しかしていねーじゃねーか!」
津雲の突っ込みに、E木は破顔一笑した。
その目は、まるで孫をあやすかのように穏やかだった。


「ハハ、そうでしたね。では、ヤクザが必要悪という私の考えを基にお尋ねします。まず、ヤクザが社会のはみ出し者や排除された者の受け皿となってきた歴史はどうお考えですか?」
「その社会的役割はヤクザが果たすべきではない。自治体なり地域住民が請け負うべきだ」
「では、我々ヤクザの力が弱まると、半グレや外国マフィアの勢力が強まることについてはどうお考えですか?」
「害虫を害虫の手で排除するのを俺はよしとしない。やはり正義の手によって撲滅すべきだ。ヤクザも半グレもマフィアも俺達が何とかする」
「では、義理や仁義など、裏社会の秩序についてはどうでしょう。私達は「堅気の人に迷惑をかけない」「物事の筋を通す」教育も担ってきました。それを排除することは、逆に治安が悪化するとは思いませんか?」
「思わないな。繰り返すがそれはヤクザの役割ではない」
.webp)
.webp)
「なるほど…」
E木は少し考え込む素振りを見せたが、すぐ笑顔に戻った。
「面白いほど話が嚙み合いませんね」
「あぁ。これが住む世界の違いなんだろう。俺も闇の中で生きていたら、多少は共感してやれたかもしれないがな」
「いいんですよ。それも世の中です。では10年後、20年後に答え合わせといきましょう。多分、私はいませんが、この約束だけは覚えていて下さい。社会が今より良くなり、悪が減っていたら津雲さんの勝ちです」
これがE木S吾との最後の会話だった。
E木はその3か月後、老衰のため亡くなった。
それを同僚から伝え聞いた津雲は、少しホッとしてしまった自分にショックを受けた。
何ということだ。
年老いたE木に、今の暴対法は無慈悲過ぎると感じていたことに気付かされたのだった。
津雲は唇を強く噛みしめて天を見上げた。
【そうだよな、E木さん…】
賃貸物件には入居できず、銀行口座を開設できず、銀行から融資も受けられず、生命保険にも入れず、車も自分名義では買えず、レジャー施設や宿泊施設では入場を制限されてしまう。
こんなクソな余生なんて、あのE木には送ってほしくなかった…。


E木との出会いは、あくまできっかけの1つでしかなかったのだが、不思議なものだ。
退職した津雲は、転がる石のようにアウトローの世界へと入り込んでいった。
まるでE木の後を追うかのように。
津雲はとにかく力が欲しかった。
力が足りないばかりに理想が理想のままで終ってしまう悔しさを何度味わってきたことか。
そして力さえあれば、正義や悪といった枠組みも飛び越えられる気がしていた。
この世には力が必要。
力のない人間が何を語っても相手にされない。
実際、津雲が声高に叫んできた正義は、警察の中でさえ「ただの中二病w」と笑われていたのだった。
しかし、力さえ持ってしまえばどうだ?
たとえ間違った意見でも、人々はとりあえず話を聞かざるを得なくなる。
ただ、それは一介の警察官であり続ける限り、難しかったのだ…。


勢いで退職した津雲は必死で考えた。
【ここからどうやって力を手に入れるか?】
辿り着いたのは、誰にでも分かるシンプルな結論だった。
今の民主、資本主義社会では、「人をたくさん集める」か「お金をたくさん集める」かだと。
そう。世の中、人をたくさん集めればお金につなげやすく、お金をたくさん集めれば人が寄ってくる。
ただ、津雲に人徳はなかった。
どんなパフォーマンスや演説をしても、万単位のファンや信者を集められないことは自分が一番よく分かっていた。
ではどうするか?
再び津雲は必死で考えた。


【やはり金を集めるしかないか…】
1000万単位では話にならない。
自分の理想を実現するには、数億、数十億の資金が必要だった。
ではどうやって集める?
現状と未来を照らし合わせた結果、迷いは消えた。
…というより選択肢は1つしかなかった。
リスク覚悟で、グレーゾーンに飛び込むしかない。
そうと決まれば、「悪は急げ」だ。
津雲は、真っ先に頭に浮かんだ悪人へ電話をかけた。


荒巻源治。
元E木組の幹部。
E木の死後、E木組は完全に解散し、組員は路頭に迷っていた。
生前、津雲が啖呵を切っていた「国や自治体や地域住民が受け皿となる」理想論は、まさに絵に描いた餅だったのだ。
1年前はバチバチに敵対していた幹部だ。すんなり仲間になってくれるとは思えない。
【それでも生きるためには、奴らも割り切ってくれるかもしれない】
そんな淡い期待もあったのだが…。


眉毛のない荒巻は、再会した早々にキレていた。
「てめぇは相変わらず年上に対して敬語も使えねぇのかよ!」
「あン? じゃない。そう…、ですね、ハハ。何か不思議ですけど、今はお互い一般市民ですものね。で、今はどんなシノギをやっているのですか?」
「ナメてんのか! パン屋のバイトだよ。朝早く起きて焼いてんだよ!」
津雲は笑いをこらえるのに必死だった。
「か、かわいいですね。に…、似合ってますよ」


「オレたちゃー殆どが中卒だからな。今更まともには働けねぇんだよ」
「なるほど。それで、さっきの話なんですけどね。ここは1つ、過去は水に流して手を組むのはいかがでしょうか?」
それを聞いた荒巻が、急に目を閉じて、しばらく沈黙した。
「まさか…な」
荒巻にしては珍しい、小さな声が部屋に舞い上がった。
「オヤジが最後に言っていたんだよ…」
「E木さんが…。何をですか?」
「津雲君は警察に向いていない。半分の確率で警察を辞めるかもしれない。そして1割の確率でお前達を頼るかもしれない。その時は彼の下について支えてやってくれってな」
「そんなことを…」
「しかし本当にそうなるとは…。分かった。さっきの話、引き受けよう。他の奴らにも連絡するから少し時間をくれ」
「ありがとうございます。よろしくお願いします」
「それと…その気持ち悪い言葉遣いはやめろ。いつもの荒い口調でいい」
「でも…」
荒巻は上を見上げて息を大きく吐いた。
そして今度は深く頭を下げた。
「今日からあなたが社長で私達はついていく社員です。そのぐらいの礼儀はわきまえています。どうぞこれからご指導、宜しくお願い致します」
荒巻は、いつまでも深く頭を下げ続けていた。


こうして元E木組の人間5人がTSUGUMOグループの初期社員となった。
津雲はカタギとしての社員教育から始めたが、さすがはE木の舎弟達だ。
ある部分では、一般人より遥かに倫理観が強かった。
一方で津雲は、警察同期で仲の良かった阿倍野潤の元を何度も訪れていた。
相談に行ったというよりは、チェックをお願いしていた。
「自分の事業計画に違法性はあるか?」と。
法律に詳しい阿倍野は最終的に断言した。
「グレーだがアウトではない」
つまり「セーフ」だ。
それでも阿倍野は、ずっと顔をしかめていた。
「津雲…覚悟はあるんだろうな。元E木組を使う情報はとうに警察に把握されているぞ。今後は徹底マークされる」
「あぁ覚悟はできている」
「あと、俺に話したのは誤算だろう。俺からのお墨付きをもらったつもりかもしれないが、逆だぞ。俺は周り以上にお前を監視する。そしていざって時は必ず俺が逮捕する」


津雲は小さく笑った。
「分かっているよ。キャリアに傷をつけたがらないお前だからこそ、あえて話したんだ」
「そうか…。何を言ってるのか分からないが…泉には話したのか?」
「いや、獅子王丸に反対されるのは分かり切っていたし、余計な心配もかけたくなかった。それにいざとなればあいつは、お前と違って情に流される可能性がある」
「まぁそうだな…」
阿倍野の顔が、一瞬だけ同期の顔に戻った。
しかしすぐに、元の険しい警察官の口調に変わった。
「今日でお前と会うのも最後だ。もう俺に連絡はするなよ」
立ち上がってドアーを開けた津雲の背中に、再び声が届けられた。
「俺は昔のお前を知っている。お前の良心はまだあると信じているぞ」
-つづく-
津雲大輔(青年期)
悪への転身(中編)
登場人物
津雲大輔
(青年期)


商取引におけるグレーゾーン。
それは、合法と非合法の境界線を狙った商売を指す。
リスクは高いのだが、ホワイトビジネスより儲けが莫大になるため、手を出そうとする人間が、常に一定数存在する。
そう。いつの時代にも、一定数の悪が存在してしまうように。
津雲の事業計画において、阿倍野が最初に指摘したのは、まさにその悪の部分だった。
限りなく「催眠商法」に近いと。


催眠商法。
集団催眠的な勧誘方法により、客の判断力や思考力を麻痺させて、高額な商品を買わせるやり方だ。
ただし、仮に津雲の事業が催眠商法だったにせよ、違法ではない。
単に、特定商取引法の規制対象であるだけなのだ。
さらに阿倍野は、クーリングオフ(契約後8日以内の取り消し)についても指摘していた。
津雲がこれから扱う商品は100万円以上の高額商品だ。
トラブルが起こる確率が非常に高いと。
それでも、そのトラブルに警察は介入できないのだった。
「民事不介入の原則」があるため、そこは弁護士の出番となるためだ。
しかし阿倍野は、津雲に何度も釘を刺していた。
「弁護士なんて関係ない。俺が怪しいと思ったらすぐに動くからな。お前は詐欺罪や特商法違反にあたらないか、常に怯えて生きるんだな」
これには大人しく聞いていた津雲も、僅かに反応したのだった。
「阿倍野、ちょっと確認していいか?」
「おう」
「俺がやろうとしているのは違法なのか?」
「違う…」
「俺がやろうとしているのは催眠商法なのか?」
「厳密には…、違う」
「ここまでありがとう。心からお前に感謝しているよ」
これで準備は整った。
いよいよTSUGUMOグループが世に出ようとしていた。


「ハイパージョーカー」
それがTSUGUMOグループが取り扱う健康器具の名前だった。
まず津雲は、30人ほどが入れそうな部屋を用意した。
そこへ温熱と電気が流れる健康増進チェアー(ハイパージョーカー)を設置する。
あとは「ハイパージョーカー無料体験会場」と銘打って、集客するだけだった。
もちろんチラシも撒くが、一番大切なのは口コミだ。
一度、体験した人が友達を連れてくる限り、無料体験は続くためだった。
津雲は、事前にあらゆる病気を勉強していた。
その人の不調を理解していれば、適切な相槌も打てるし、簡単なアドバイスもできるし、同じ症状で苦しむ人の体験談も紹介できる。
もちろん医師法があるので、確定診断は絶対にしない。
診療もしないし処方箋を出すこともないが、パソコンやカルテばかり見て患者と向き合おうとしない医者に不満を持っている層にとって、津雲との会話は救いとなった。


ハイパージョーカーを体験して気に入ってもらう。
⇒気に入って通ってもらう。
⇒無料体験を継続するために友達を誘ってもらう。
⇒友達が体験して気に入ってもらう。
これが津雲の事業における成功サイクルだった。
ただ、これを実現するには、実際に体験者の症状が「良化」しなければならない。
どんなに津雲の健康講座が楽しくても、良くならなければ、気に入ることも通うこともないのだ。
それでも津雲は、絶対的な自信を持っていた。
少なくても、体験者の7割以上は、本当に体の症状が良くなると。
その種明かしはこうだ。
まず根本の考え方として、「体の隅々まで血流を良くする」という大原則がある。
「血流が良くなれば免疫力が上がり、自分の中にある自然治癒力が高まる」ためだ。
津雲はこの言葉を、お客さんに何度も繰り返すことになる。
ハイパージョーカーの温熱と高圧電位こそが血流を促すのだと。
実際、ハイパージョーカーに座ればお尻から温熱が伝わり、時にはピリリとした電気刺激も感じることができる。
世界中のどんな学者を集めても、「血流が良くなる可能性は高い」のだった。


そして重要なのはここからだ。
津雲という人間に対する信頼と好意は、そのままハイパージョーカーへも向けられる。
津雲は、健康講座を開くだけでなく、1人1人の話もじっくり聞く。
しかも1日100人以上、週に1000人以上訪れるお客さんの全てのフルネームを記憶して、ちゃんと名前で対話をしているのだった。
仮に同じ治療なら、好きな人から受けるのと嫌いな人から受けるのとでは、効果は雲泥の差になる。
「病は気から」という言葉がある。
それが全てではないが、世の中には、そう思わざるを得ないような事例も存在する。
ならば「健康も気から」作り出すことは可能だろう。
会場は、いつも明るい笑い声で溢れた。
津雲の毒舌を織り交ぜたユーモアもそうだが、顔馴染みになった仲間達が集まれば自然と笑いも出る。
そして言うまでもなく、「笑い」の健康効果は下手な薬より高い。


津雲の天才的なところは、会場の大半を津雲信者で埋められた点だった。
E木組の元幹部は、「社長なら超一流の詐欺師になれますよ」と褒め称えた。
システムとしてはこうだ。
津雲は、通うことを決して強制しない。
「体の改善が見られなければ、通うのを止めてください」とまで言う。
そのため会場に集まるのは、体調が良くなったリピーターと半信半疑で初体験する人となる。
そしてその割合を、常に9対1に調整した。
おそらく1割の初体験の人は感動するはずだ。
最初は椅子の温かさと電気刺激に。
次に、津雲が自分の体が良くなる道筋をハッキリと示してくれることに。
最後に、実際に良くなったリピーター達の喜びの発表が、怒涛の如く続くことに。
会場はすでに、希望しかない天国なのだ。


1か月ほど経った頃には、「ハイパージョーカーを今すぐ売ってくれ!」というリピーターが複数現れた。
しかし津雲は「無料体験期間中」を盾に絶対売らなかった。
そのため、買いたくて買いたくてしょうがない信者達が、毎日会場を訪れることとなった。
狂信的な信者が増えるとどうなるか?
会場の熱気は凄まじいものになり、言わば、集団催眠状態になる。
津雲はそれが狙いだった。
集団催眠状態は素晴らしい効果を生み出す。
車椅子で訪れた人が帰りはスタスタ歩いて帰る奇跡など、すでに会場にいる人は、当たり前のように受け入れていた。
集団催眠状態を作り出し、心身に良い影響を与えられる人間は、世界においても少数だ。
津雲はカリスマ教祖、もしくはゴッドハンドを持つ治療家のような位置を、システムと才能で作り出したことになる。
すでに隣に座っている1人1人が、そして会場全体のエネルギーが「良薬」になっているのだった。
そしてこの熱気の力こそが、阿倍野に何度も確認してもらった点でもある。
TSUGUMOグループがやろうとしているのは、「催眠商法」ではなく「催眠療法」なのだと。


3か月も経つと、無料体験会場は大盛況となり、中に入れない人で溢れた。
あまりの混雑ぶりに周辺地域からの苦情も入り、時々、パトカーが巡回に来た。
過去のトラウマからか、社員の一部はそれに怯んだが、津雲自身はどこ吹く風だった。
しかし、今日のパトカー3台は、意味が違った。
社員やお客さんの車が傷つけられる事案が連続で起きたからだった。
明らかに故意の嫌がらせだが、今日で4日目となる。
それは、警察の力では解決できないことも意味していた。
その夜。
さすがの津雲も頭を抱えていた。
ある程度は予測していたが、この手の嫌がらせには打開策が見えない。
そこへ、専務の柄本剛士が声をかけてきた。
「夕方に見回った時、昔、見た顔の奴がいました。事務所も分かっていますので、ちょっと今から行ってきます」
「そうか…。やはりそっち系だよな…。任せるけど、くれぐれもトラブルは起こすなよ」
「フッ、『蛇の道は蛇』ですからね。お任せください」
「それだよ怖いなぁ。いい加減、今の立ち位置に慣れろ」
柄本は神妙に頭を下げた。
「すみません社長、『餅は餅屋』の間違いでした」


次の日から嫌がらせはピタリと止んだ。
「ありがとう。助かったよ」
津雲は柄本を呼んでねぎらった。
「一応確認するけど、暴力はふるってないよな?」
「当然です。話し合いのみで分かってくれました」
「お前、口下手なのにホントかよ?」
「はい。社長にいつも言われているように、真心こめて笑顔で話しただけです」
「それだっ! かわいそうに。絶対笑わない過去のお前を知っている者からしたら、さぞかし怖かったろうなぁ」
警察で解決できないケースは、世の中にごまんとある。
それを元ヤクザが簡単に解決した。そんなケースも現実にはある。
津雲は今更ながら、生意気だった過去の自分が恥ずかしくなった。
そして「必要悪」の存在を説いていたE木へ、そっと手を合わせたのだった。
-つづく-
津雲大輔(中年期)
悪への転身(後編)
登場人物
津雲大輔
(中年期)


5か月が経っても、ハイパージョーカーの人気は留まることを知らなかった。
会場を広くし、回転数も増やしたが、会場の周りには人が溢れた。
初日は4人のお客さんで始まった無料体験。
それが今や、1日700人。1週間で5000人に達した。
津雲は、大幅に増員させた社員を集めると、いよいよ販売に踏み切ることを伝えた。


翌日から、会場には「無料体験終了まであと30日」の看板が掲げられた。
ここからは、毎日、カウントダウンが進むのだった。
信者達は、この30日以内に様々な選択を迫られる。
・次の無料体験会場となる、60キロ離れた隣の県まで通う。
・体調が良くなったことに満足し、終了する。
・健康を維持するため、ハイパージョーカーを購入する
津雲はいずれの選択でも「可」であることを強調した。
ただし、ハイパージョーカーは「本当に変化があった人」「良くなった人」にしか売らない条件をつけた。
形態としては「押し売り」の真逆なので、「引き売り」となる。
つくづく面白いのは、津雲が売るのを渋るほど、商品の心理的価値が上がり、欲しがる人が増えたことだった。


実の話、津雲のビジネスは、総体験者数が5000人になった時点で完結していた。その時点で、成功は約束されていたのだ。
津雲が気にしていたのは、常に母数だった。
体験者全員に気に入ってもらう必要はなく、半分の50%でも2500人の信者が誕生する。
その中で、実際に買ってくれるのは、わずか1割でもいい。
1割でも、250人×100万円で2億5千万円の売り上げとなる。
津雲が一貫して強気で、媚びる必要もなかったのは、この母数コントロールができていたからだった。


おそらく…ここまでの話は一般の人にとって想像もつかないだろう。
空想やマンガの世界の話かと思うかもしれない。
しかし、これが現実だった。
今も似たようなことが、いや、もっと悪質なことも、日本のどこかで行われている。
これがグレーゾーンビジネスなのだ。
結局、TSUGUMOグループは、半年間で4億2千万円を売り上げた。
かかった経費は、全員の人件費を合わせても1億円。
純利益3億2千万円という途方もない数字を残して、1回目のビジネスを終えたのだった。
だが、これで終わりではない。
2回目のビジネスが、1週間後に場所を変えて始まる。
そのための準備は、すでに別部隊の社員が整えていたのだった。
津雲の計画では、これをあと5回。今後3年という時間をかけて行うのだ。


津雲にとって唯一の誤算は、税金だった。
せいぜい納めるのは3割程度だと思っていたのだが、初年度は5割近くを持っていかれてしまった。
激怒した津雲は、すぐに顧問税理士をクビにし、有名な会計事務所に鞍替えをした。
どんな世界にもグレーゾーンはある。
税金で言えば、脱税(ブラック)と節税(ホワイト)の間に、グレーがあるということだ。
津雲は、担当の公認会計士へ、くれぐれも脱税だけ「は」、しないようにと釘をさした。
有能な人間なら、それで全てを汲み取るものだ。
会計事務所からは、積極的な設備投資を打診された。
利益をプールするのではなく、どんどん次の準備を進めていったほうがいいと。
そのため津雲は、計画を前倒しして、土地や建物を買う準備を始めることとなった。


津雲は最初から、ハイパージョーカービジネスは3年で卒業すると決めていた。
社員の多くは「これだけ儲かるのになぜ3年しかやらないのか?」と首を傾げた。
しかし、どう考えてもこのビジネスモデルは3年が限界だった。
まず、津雲の心身が持たない。
100人以上の狂信的信者のケアを24時間365日。
例えば、夜中の2時に、1人暮らしのお婆ちゃんから「眠れない」との電話がかかってくる。それはザラだ。
そんな時も津雲は、話をいつまでも聞き続け、最後は「明日、ハイパージョーカーに座りに来てくださいね」と声をかけたのだった。
加えて、「狩場」の問題がある。
日本全国、どこでもこのビジネスが成立するわけではない。
やはり適した場所と向かない場所に分かれるのだ。
地域における限られた「狩場」。
その場で根こそぎ狩っていけば、しばらくそこは不毛の地となる。
それを何年も繰り返せば、このビジネスが先細りしていくのは明らかだった。
最後に、存続自体が本当にギリギリなのだ。
ちょっとでも気を許せば、すぐに警察に捕まる気配は常に感じていたし、同業他社からのマークや狩場争いにも厳しいものがあった。
元々、事業資金作りが目的で、延々と金を稼ぎたかったわけでもない。
だからこそ津雲は計画通り、「ハイパージョーカー販売」を6回行った。
そして粛々と、2003年6月30日に完全撤退したのだった。
総売り上げは、ちょっとした台風並みのスケールだったが、税金を20億円強、納めたことも付け加えておく。
いよいよTSUGUMOグループは、次のステップに入るのだ。


2004年8月25日。20時半。
泉獅子王丸と阿倍野潤は、仕事終わりに居酒屋へ寄っていた。
2人でお酒を飲むのは久しぶりだった。
話題は、警察内部で再び名前が出てくるようになった津雲大輔のことだった。
「あいつはどこまでもグレーゾーンで勝負する気なんだな。レストランやカフェで止めておけば俺も目を瞑ったが、バー、ゲームセンター、パチンコ・スロット店ときたら、もう黙ってられないぞ」
それを聞いた泉獅子王丸が少し首を傾げた。
「どうだろう。グレーでも管轄は俺達、警察になるんだから、これまでの怪しげな商売よりリスクは減るんじゃないか。警察の監視下ということは、警察に守られているとも言えるからな」
「ん、そうとも言えるか…。確かに立場上は俺達が親で、あいつは子供みたいなものだよな。そう考えると気分は悪くないな、ハハッ」
その後、しばらくは昔話を含めた他愛もない話が続いた。
同期の中では、泉、津雲、阿倍野の3人が特に仲が良く、色々な話をしたものだった。


1時間ほど経過した頃、阿倍野がため息をつくように口を開いた。
「しかしあいつは向こう側に行ったんだと改めて感じるよ…。もう俺達とは住む世界が違う。あいつの周りには今や問題のある奴ばかりだ。昔は正義感が強い奴だと思っていたけど、本質は堕落した、心の弱いクズだったんだな」
「取り消せ」獅子王丸が静かに凄んだ。
「ん? どうした泉?」
「あいつは罪へ転身したわけではない。悪への転身だ」
「大差ないと思うが…」
「俺も最初はショックだった。しかし今は、あいつが警察を辞めて悪へと潜入してくれたことを、助かるしありがたいと思っている」
「潜入? どういう意味だ?」
「今の社会には正論だけでは救えない人達がいる。今の社会問題を解決するのに善人だけでは限界がある。ではどうする? どうやって救う? どのように解決する?!」
獅子王丸の声が次第にヒートアップしていった。
阿倍野は慌てて「シーッ」とブレーキをかけたが、勢いは止まらなかった。
「大輔は自分を捨てたんだ! 皆のために! 誰からも誉められることのない、後ろ指を指されるその道を、光を浴びることのない世界を! 平穏の存在しない修羅の道を! 一体誰がそれを選べる!?」
阿倍野はまず、周囲の冷たい視線に対して方々へ頭を下げた。そして言葉を続けた。
「いやいや。泉は津雲を買い被り過ぎだよ。あと飲み過ぎだな。ちょっと水を飲め」
渡された水を一気に飲み干した獅子王丸は、空になったグラスを力強くテーブルに置いて呟いた。
「俺達2人はまだ、警察内部でいいカッコをしている。それが全てだ…」


2003年の下半期。
TSUGUMOグループは、カフェやバーやゲームセンターやパチンコ・スロット店を次々と展開させていった。
それは、同業他社にとっては脅威でしかなかった。
黒船来襲。
まさに当該地域においては、そう感じたことだろう。
そもそも名前は普通でも、元警察官と元ヤクザが手を組んでいる得体の知れない会社なのだ。
向き合い方が分からない。
また、銀行融資が受けられない業界において、異例とも言える出店スピードは、様々な噂を生み出した。
「健康器具販売の成功で無尽蔵の資金を持っている」
「E木組の隠し財産を使っている」
「警察がバックについている」
実際、TSUGUMOとの間に起きたトラブルの殆どは、TSUGUMOと敵対する側が捕まったり指導を受けていたので、一層不気味さが増した。


社会は様々な顔を持つ。
健全と不健全。表と裏。理性と欲望。光と闇。
TSUGUMOグループが関わっているのは、紛れもなく後者だ。
2014年。
TSUGUMOは、わずか10年あまりで、地域における後者の社会を支配した。
いや、支配したという表現は適切ではない。
影響下においた、意識せざるを得なくした、というニュアンスのほうが正確だ。
もうこの地域でTSUGUMOグループを敵に回そうと考える人間はおらず、自分達の店に実害が出ないよう、もしくは高く買い取ってもらおうと画策する人間が大勢を占めた。
一般の人は気付いていないだろう。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で規定された店の総数は変わっていないため、見た目も派手さも街に変化はないのだ。
既存のお店の中身がTSUGUMOに置き換わったり、TSUGUMOに吸収合併されていっただけなのだった。
それでも裏社会に関わる人間で、津雲大輔の名前を知らない人間は、もういない。
何をするにせよ、多少は津雲の顔色を伺う。
味方も多いが敵も多い。どちらにせよ無関心ではいられなくなる。
トップに立つとはそういうことだった。


力が欲しくて警察を辞めた人間。
それが20年あまりの時間をかけて、多少なりとも力を持てるようになった。
金も人も、昔では考えられないくらい掌握している。
しかし津雲は、驚くほど何もしなかった。
街にとって良いことも悪いこともしなかった。
表向きの権力はゼロだ。名誉もない。
公的な力で言えば、地区の民生委員にも劣る。
市民の誰も、津雲を見ても分からないし、隣を通り過ぎても気付かない。
この辺りでは潜在的な巨大な力を持っていることも、市民生活に影響を出せる人間であることも。
例えば、津雲がその気になれば、思い通りに動く議員を10人は送り出せる。
それを人々は、フィクサーと呼ぶ。
しかし津雲は動かない。
なぜ津雲は動かないのか? どうして何もしないのか?


すでに1つの目的が達成されていたことは、挙げられるだろう。
この世の中、ロクでもない人間に大金や権力を持たせるとロクなことにならない。
大金や力とは、トランプでいう「ジョーカー」みたいなものだ。
だからこそ、それが他に渡らないようにTSUGUMOグループがキープしている。
ただキープしているだけで行使はしない。
それも大きな意味を持つ。
実は、2010年から少しずつ、この地域の犯罪件数が減っていた。
ゼロになることはないだろうが、特に凶悪犯罪が減ったことは、警察内部でも評価されていた。(特に阿倍野の出世に役立った)
もちろんそれがTSUGUMOグループのおかげかは、誰にも分からない。仮にそうだとしても警察は絶対に認めない。


TSUGUMOグループが持つ潜在的な力。
いつかはそれを使う時が来るのかもしれない。
ただ、先日の役員会では「次のターニングポイントが来るまでは待機」との社長命令がなされた。
それに対する憶測は流れたが、決定自体に異論は出なかった。
理由は明白だ。
社長以下、全員が分かっていたからだ。
自分達がロクでもない人間であることを。
そして願うように待っていたからだ。
安心してバトンを渡せる人間が現れることを。
-fin-



津雲さんの怖いイメージは変わりませんが、理解不能だった恐れは無くなった気がしますぅ



獅子王丸さんが津雲さんをネッキャンに誘ったのだから、まぁこのような背景だろうとは想像していました



称賛はできません。ただ、同じ空気を吸うことに抵抗は無くなりました



って…ボス若い時、めっちゃイケメンじゃないっスかー!
何か悔しいです!
佐々木拓海(18歳当時)
永遠の憧れの先輩
登場人物
佐々木拓海
(18歳当時)


高3になって初めてバイトを始めた佐々木拓海。
そんな拓海にすぐ、憧れの先輩ができた。
名前は「淀野夢菜」
同じコンビニでバイトをしている、お姉さんタイプの大学1年生だった。
2人は、同じシフト「平日の夕方」を希望しており、頻繁に顔を合わせた。
そして元々が人好きな拓海だ。夢菜とは、すぐに仲良くなった。
バイト自体は、ほぼ同時期に始めたのだが、優秀なのは圧倒的に夢菜だった。
夢菜は面倒見がよく、拓海が覚えきれていない仕事を教えてくれたり、ミスをカバーしてくれたりした。
また、会う度に「佐々木君ってホント面白いね!」と言ってくれた。
そして拓海も、夢菜の持つ7色の笑顔を見るのが楽しみとなっていた。


中学生以上の男性なら分かると思うが、殆どの男は、迷信に似た恋愛マニュアルを隠し持っている。
面白い男ほどモテる。
面倒を見てくれる女性は、すでに母性本能がくすぐられている。
会う回数が増えるほど、好意は高まる。
大抵は、その後に「ただしイケメンに限る」との注意書きがつくのだが…。
恋愛経験の疎い拓海は、この3つだけでイケると勘違いをしてしまった。
夢菜と出会ってわずか1か月後だ。
サプライズと言えばサプライズ…。
2人のバイトが重なった日に、あっさり告白したのだった。


告白したのは、ロマンティックさが最も足りない午後3時。
夢菜がコンビニの制服に着替えた直後だった。
拓海としては、今回だけは面白いことを言ったつもりはないのだが、夢菜はいつものように笑いながら返してきた。
「理由はないけどゴメン、無理w」
言い終えると、夢菜はすぐに自分の仕事に取り掛かった。
断られると思っていなかった楽観主義の拓海でも、多少は気まずい気持ちになった。
【言わなければ良かった…】
そんな後悔の念も生まれていた。


微妙な空気の中、それぞれの仕事をこなしていた30分後。
コンビニとしては珍しい、高額商品ばかりをカゴに入れた年配の女性が、拓海のレジへやってきた。
まさかこの女性が、数分後に羽の生えた天使に見えるとは、拓海には知る由もなかったが。
「ありがとうございます。29700円になりますが、お支払いはどうなさいますか?」
女性がもどかしそうに答えた。
「えーとアレ…、アレよお兄さん。ひと思いにやっちゃいたいんだけど…」
「え?! 僕をですか?」
拓海が恐怖に似た甲高い声を出すと、隣のレジにいた夢菜が口を挟んできた。
「かしこまりました。クレジットの一括払いですね」
「なーるほどね…」
拓海はそう呟くと、夢菜に軽くお礼の会釈をした。
そして夢菜からは、かわいらしいウィンクが返ってきた。
【うぉーーーっ】
クレジット払いの手続きをしながら、拓海は幸せを噛みしめた。
気まずさは完全に消えていた。これでいつもの2人に戻れた気がした。
いや、むしろ少し進展した気すらする!
【ありがとう! おばさま!】


拓海がフラれてすぐに立ち上がり、2週間が経った頃だった。
年齢は20歳くらいでおとなしめの男性。悪く言えば、ネクラな常連客が来店した。
本当は、レジ担当が夢菜希望だったのだろう。キョロキョロしても姿がないことを確認すると、渋々、拓海の前に立った。
そしておにぎり1個とクーポン券を差し出してきた。
「はいっ、失礼しますねー」
拓海はいつも通り明るく対応した。
しかしクーポンを確認するなり笑い出した。
「あはは、これ期限切れてますし、ライバル店のクーポンですねw」
完全に固まってしまった男性を見た夢菜が、商品補充の手を止めてすぐに対応した。
「あ、大丈夫ですよ。ウチのクーポンと交換しますから」
そう言いながら、胸のポケットからクーポンを取り出して、拓海に優しく手渡した。
さらには、すぐさまバックヤードに向かい、景品のペットボトルのお茶を持ってきた。
男性客は小さい声を絞り出した。
「ありがとうございます…」
夢菜もニッコリ笑って返した。
「こちらこそ、他店ではなくウチに来ていただき、ありがとうございました!」
すぐさま拓海も続いた。
「ありがとうございましたーっ」


男性客を見送りながら、拓海はいたく感心した。
「先輩、凄い対応力っすねー。惚れ直しました。付き合ってください!」
「ありがと。あと懲りないコね…。でも、私も佐々木君と一緒の仕事は楽しいわ」
夢菜が商品補充に戻る際、サラリと先ほどの営業用とは違う笑顔を見せた。
そう。他の店員がいる時、この顔はしない。
7つある内、自分だけに見せてくれる一瞬の「素笑顔」。
【あぁ、これ以上の幸せがあるのだろうかー?】
あ、そういえば、マニュアルに書いてあった。
『素の笑顔を見せてくれる女性はー』
【いやいや!もうさすがに懲りたっ!】
苦笑しながらも拓海は強く思った。
【それでも、この笑顔だけは見たい! 何度でも!】


7月中旬。
最近の2人は、バイトの終わり時間が同じだと、最寄り駅まで一緒に歩いて帰るようになっていた。
拓海にとっては、去年までは想像できなかった、青春の貴重な1ページとなる。
加えて「先輩」と呼んでいたのが「夢菜ちゃん」に、「佐々木君」と呼ばれていたのが「拓海くん」に変わっていた。
「ねぇ拓海くん。こんなにシフト入れて、夏期講習は大丈夫なの?」
夢菜がドリンクを飲む手を止めて、隣を歩く拓海に話しかけてきた。
「はい。行くつもりないんで」
「えーっ、受験、大丈夫?」
「はい。ちゃんと家で勉強もやっています。僕は勉強がんばって、夢菜ちゃんの通っている大学に行きたいんです」
「そうなんだ。言ってなかったっけ? 私、女子大よ」
「僕ちゃんは、やればできる人間なので大丈夫です!」
「面白-い。じゃあ来年の春、キャンパスで会いましょうね」
「ウッス。それで…、夢菜ちゃんと付き合えたら、さらに勉強がんばれるんですけど…」
ドリンクを持っていない拓海は、自分の唾をゴクリと飲み込んだ。


「ごめん無理」
夢菜が笑った。
「ほら!私の飲みかけのレモンティーあげるから、それでがんばって!」
「おーっ、ありがとうございますー!」
フッてフラれるを繰り返す2人の関係。
つかず離れずの友達以上恋人未満…。
拓海の軽い恋愛ジャブには、夢菜も軽くジャブで応戦する。
しかしお互い、とどめとなる渾身のストレートは打ってこない。
甘噛みを楽しんでいるのか…、深く踏み込むのが怖いのか。
それは本人達にも分からなかった。


9月20日。
この日はちょっとした事件があった。
始まりは、夢菜のレジに、足元のしっかりしないお婆ちゃんが来たことだった。
初めて見るお客さんだったが、問題はカゴに入れてある大量のプリペイドカードだ。
夢菜が近くにいた拓海にそっと声をかけた。
「拓海くん、これって…」
確かに、第三者でしかないバイトにとっては難しい局面だ。
「うん、ちょっとここは僕に任せてください」
拓海が夢菜に代わって、お婆ちゃんの前に立った。
最近少しずつ、拓海が夢菜をヘルプする場面も増えてきたのだった。


「はい、お婆ちゃん、ちょっと確認していきますよー。まずこのA〇a〇nギフトカードですけど、これはA〇a〇nでの商品を買う時に使いますけど、合っていますかー?」
「はい、合っていますよ。A〇a〇nはジャングルじゃなくて買うところです」
「正解。では、このGo〇gle Pl〇y カードとニン〇ンドープリペイドカードについてです。これってネット上のアプリやゲームで使うものなんですけど、お婆ちゃん、使います?」
「ゲーム…。あぁ孫はゲームをよくやるんですよ」
「なるほど。最後にこのビッ〇キャッシュカードですけどね。これはSNSや動画や音楽などのウェブサービスを買えるものなんですけど、これもお孫さんでしょうか?」
「さぁ…。私はお兄さんの言っている言葉が分かりません。ただ、孫に頼まれたものをメモして買いに来ただけなので…」
そう言うと、手書きのメモをレジ台の上に置いた。
慌てて殴り書きした後に、すぐに家を飛び出してきたのだろうか。
字は勢いよく乱れていた。
拓海は、溢れ出てくる感情をできるだけ抑え、静かで低めの声を出した。
「お婆ちゃん、今、お孫さんは家にいますか?」
「いえ、九州にいるんで電話で頼まれましたよ。これ東京にしか売ってないんでしょ?」
「お婆ちゃん…」
拓海が視線を落としたタイミングで、夢菜が近付き、そっと耳打ちしてきた。
「警察、あと5分くらいで来てくれるって…」
「うん、ありがとうございます!」
お互い、いつもとは違う力強いアイコンタクトをした。
善良なお年寄りを騙すオレオレ詐欺。
2人はそれを絶対に許すことができなかった。


10月9日。
拓海と夢菜は、事前にオレオレ詐欺を防いだとして、警察から感謝状を贈られた。
当初、夢菜は「私は警察に電話しただけなので…」と辞退したが、拓海が必死に説得した。
「あれは二人で初めての、記念すべき共同作業だったんですよ!」と。
「何?その結婚式みたいなセリフ」
夢菜はそう笑いながら、少し恥ずかしそうな表情を見せた。
地域の新聞にも載ったその写真を、拓海は新聞社にお願いして手に入れた。
拓海にとっては、憧れの人と初めてのツーショット写真。
それは拓海の大切な宝物となった。


2022年4月1日。
拓海は無事、大学生になれた。
できる限りの努力はしたのだが、夢菜のいる大学には入学できなかった。
その気になれば、すぐにでも夢菜が待つキャンパスに忍び込むことはできる。
が、間違いなく通報されるだろう。
もちろんそこまでする必要はない。
これまでと同じ時間帯でバイトに入れるので、夢菜とは今まで通り会える。
夢菜は「3年生になったら忙しくなるのでバイトは辞める」と言っていたが、逆を言えば、あと1年間はチャンスがあるということだ。
【サクラも咲いていることだし、ここはポジティブに行こう!】


普通、人は、何回フラれたら諦めるのだろう?
拓海は夢菜に、これまで10回以上、フラれていた。
確かにそれは、全て相も変わらぬ軽い感じのやり取りだった。
そしてフラれたからと言って、憧れの気持ちが消えるわけでもなかった。
「彼女になって下さい、お願いします!」
「ハイ無理です、ごめんなさい!」
あまりにも流れ作業的な会話なので、いつしか2人とも定型句のような感覚になっていた。
「今日も暑い(寒い)ですねー」「そうですねー」的な。
夢菜は一度、「拓海君のアプローチは重たくないから、こんな風に断れて、その後も楽なんだー」と笑ったことがある。
拓海は「言葉に重たさがないから、こんなに断られちゃうんですかね…」と嘆いたこともある。
その時だけだ。夢菜が少し寂しげに笑ったのは。
「あーちょっとあるかも。真剣なのか冗談なのか分からない時もあるから」


佐々木拓海と淀野夢菜。
2人の仲の良さは誰もが羨ましがるほどになっていた。
パイトの終わる時間が1時間程度のズレであれば、いつもどちらかが待っているのだ。
夢菜は、待っている拓海に対して、ありがたくも申し訳ない気持ちを抱くのだが、拓海など、奥で憧れの夢菜が自分を待ってくれていると考えただけで、仕事中でもたまらない気持ちになるのだった。
2人の仲は、出会った頃よりさらに良くなっていた。
駅で別れていた帰り道も、時々はご飯を一緒に食べて帰ることも増えた。
ただ、公式には、ただのバイト仲間で、友達でも恋人でもない。
駅の階段で、疲れた夢菜の手を拓海が引いて登ることもあれば、なかなか帰りたがらない拓海の背中を夢菜が全力で押して歩く時もあった。
「おいしいからこれ食べてみてー」と夢菜が食べかけのパスタを譲ることもあったし、雨の日など「夢菜ちゃん、下着透けているからっ!」と拓海が照れながら注意することもあった。
しかし、休みの日にわざわざ会うことはなかったし、どんなに顔が近付く場面があってもキスには至らなかった。


そんな「特殊な仲良し」の関係性を、周りに説明するのは、極めて難しい。
適切な単語は世界中のどこを探してもなかったし、2人にしか分からない繊細なものだった。
無理に言葉にすれば、ただの陳腐になってしまう。
それを承知で言えば…、
「ちょうどいい感じ」。
確かに、最近の2人はこの言葉をちょくちょく使う。
出会った頃からいい感じだったが、今は「超ちょうどいい」のだ。
もちろん拓海は、出会ってから常に、先の段階へ進もうとアプローチを続けている。
これからも夢菜に告白を続けるだろう。
対する夢菜は、今の微妙な関係を壊さないためにブレーキをかけ続ける。
そして全体としては、少しずつ少しずつ進展している。
駆け引きとは違う。
2人とも、2人にとってより良い道を探している。
ただ、やり方の違いから生まれる微妙な綱引き。揺れ動く感じ。
これら全てがどこか心地よく、ちょうどいい感じなのだった。
今は2022年の9月5日。
この先、2人がどうなるかは誰にも分からない。
確実なのは、夢菜が、この青春アイコン的バイトを辞めるまで、あと半年ということだけだった。
-f i n-



拓海はBサインは休んでも、コンビニバイトだけは絶対に休まないからね!



拓海…、その状態を「モラトリアムラブ」と言うんだよ。羨ましい



えっ!?そうなんですね!?



すみませんウソです…。羨ましいのはホントです
高見宗太郎(19歳~)
宗太郎の再スタート
登場人物
高見宗太郎
(19歳~)


高見宗太郎は、19歳になった次の日に大学を休学した。
そして寝食以外の空いた時間をバイトに費やし、ガンガン旅の資金を稼いだ。
もちろん両親には内緒だった。
迎えた1982年8月18日。
いよいよ宗太郎の1人旅が九州から始まった。
傍から見れば、好き勝手な放浪の旅にしか見えないだろう。
ただ、宗太郎は、精神的に切羽詰まっていたのだ。
【自分は一体何者なのか?】
【これから何をすべきなのか?】
それが分からず、何も手につかなくなったのだ。
そう。言わばこれは、大人になる直前の「人生の意味を探す旅」だった。


「あなたの人生の意味は何ですか?」
宗太郎はたくさんの人に問いかけた。
宮崎、福岡、広島、兵庫、滋賀、長野、栃木…。
どこを巡っても、しっくりくる答えは聞けず、頭の霧は晴れなかった。
県民性の違いはあれど、皆、そこまで悩んでいるようには見えなかった。
「意味など必要ない。ただ生きているだけで素晴らしいのだ」
そんな声も多く聞いた。
確かにそれも正論だった。
意味がなければ生きるエネルギーが湧かない自分のほうが異常なのかもしれない。
宗太郎は、旅の意義さえ分からなくなり、夏台風と併せて迷走しながら北上を続けた。
最終的なゴールとなった岩手県へ上陸したのは、11月中旬のことだった。


ここは岩手県、盛岡競馬場。
宗太郎は、旅の資金作りのために競馬場へ来ているわけではなかった。
考えすぎて頭がパンクしそうになった時、ギャンブルが救いになることを学習していたからだった。
大切なお金を賭ける行為。
その際に出る本能的なアドレナリンが、一時の「うつ気分」を解消してくれ、生きる活力をもらえるからだった。
第2レースが終了したばかりの場内には、歓声でも溜息でもない微妙な空気が漂っていた。
この空気は全国共通だったので、よく分かる。
圧倒的な1番人気の逃げ馬が、3着に逃げ残ったのだ。
勝ってはいないが、馬券的に最低限の仕事はしている。
単勝馬券は外しても複勝馬券は取っている。馬連は当たっていないがワイド馬券なら的中だ。
そんな誉めも罵倒もできない絶妙な着順なのだった。


「ちょいと」
宗太郎は、背後から見知らぬ老人に声をかけられた。
「お兄さんはこのレース、どのような馬券を買われたのかね?」
無視したかったが、ギャンブル場としては、完全にドレスコードを間違えている紺のブレザーとグレーのスラックスがどうしても気になる。
そしてつい答えてしまった。
「えっと、1番人気のスットコサンダーの単勝に9千円、複勝に9万1千円ですが、あなたは?」
老人は、快活な声を出して笑った。
「オホホ、やはりワシの目に狂いはなかったの。10万円を使って100円を取りにいくとは、とんでもない下手くそじゃ!」
「はぁ?」
「あぁ、ワシは買わんよ。人間を見に来ているだけじゃからの」
「はぁ…」
これが後の恩人となる天川玄作とのファースト・コンタクトだった。
この会話から始まったドタバタがきっかけで、5ヶ月後には天川が教鞭をとる大学に編入したのだった。
しかも、昔から軽蔑していた心理学部へ。


なぜ岩手の競馬場という特殊な場所で、宗太郎の「自分探しの旅」が終了したのか?
答えはシンプルだ。
天川玄作が、宗太郎の疑問に全て答えてくれたからだった。
最後の決め手となったのが、この言葉だ。
「人生に意味などない。自ら意味を作り出していくのが人生なのだ」
オーストリアの精神分析学者、アルフレッド・アドラーの言葉…らしい。
…が、宗太郎には、誰の言葉かは関係なかった。
この言葉を頭の中で3回繰り返した時、全ての霧が晴れたからだ。
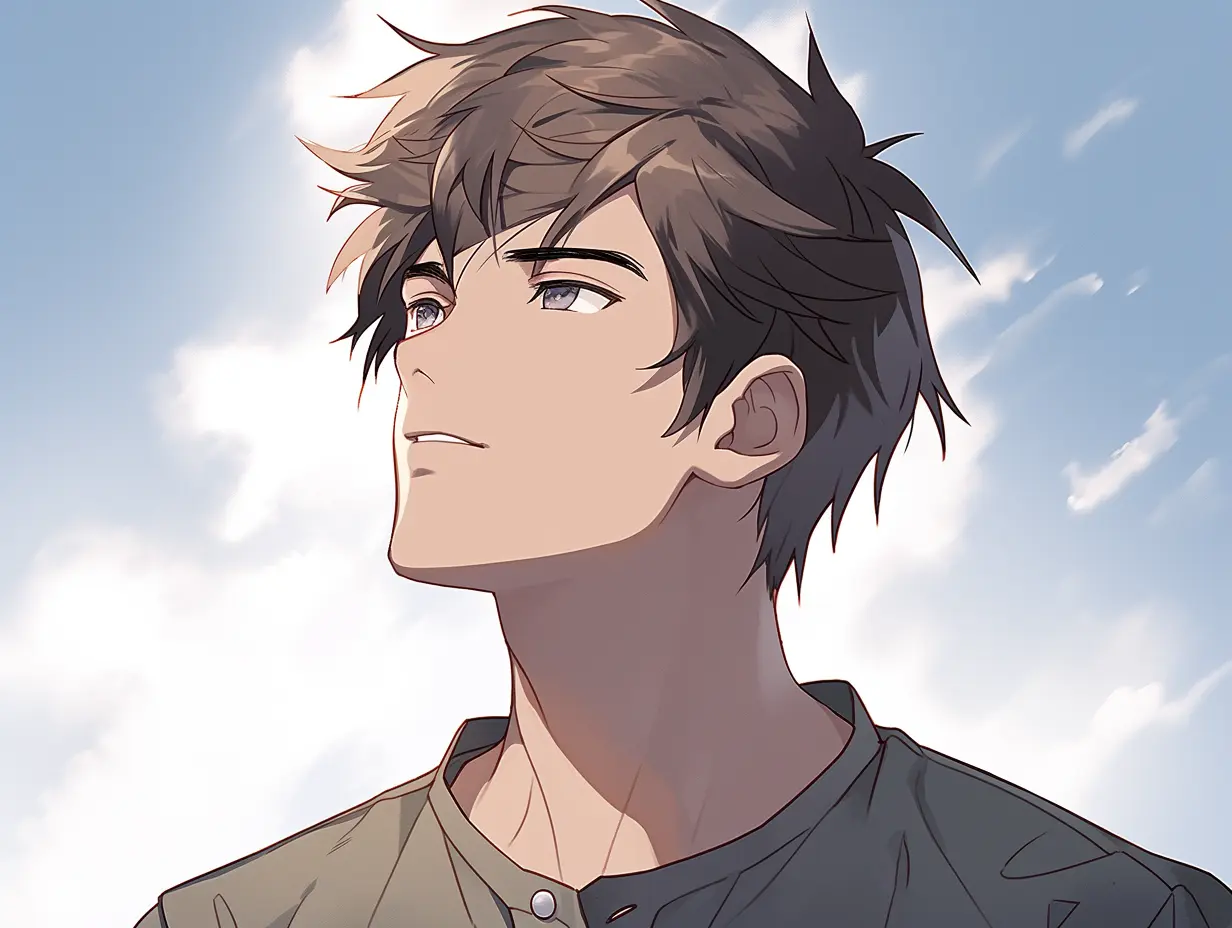
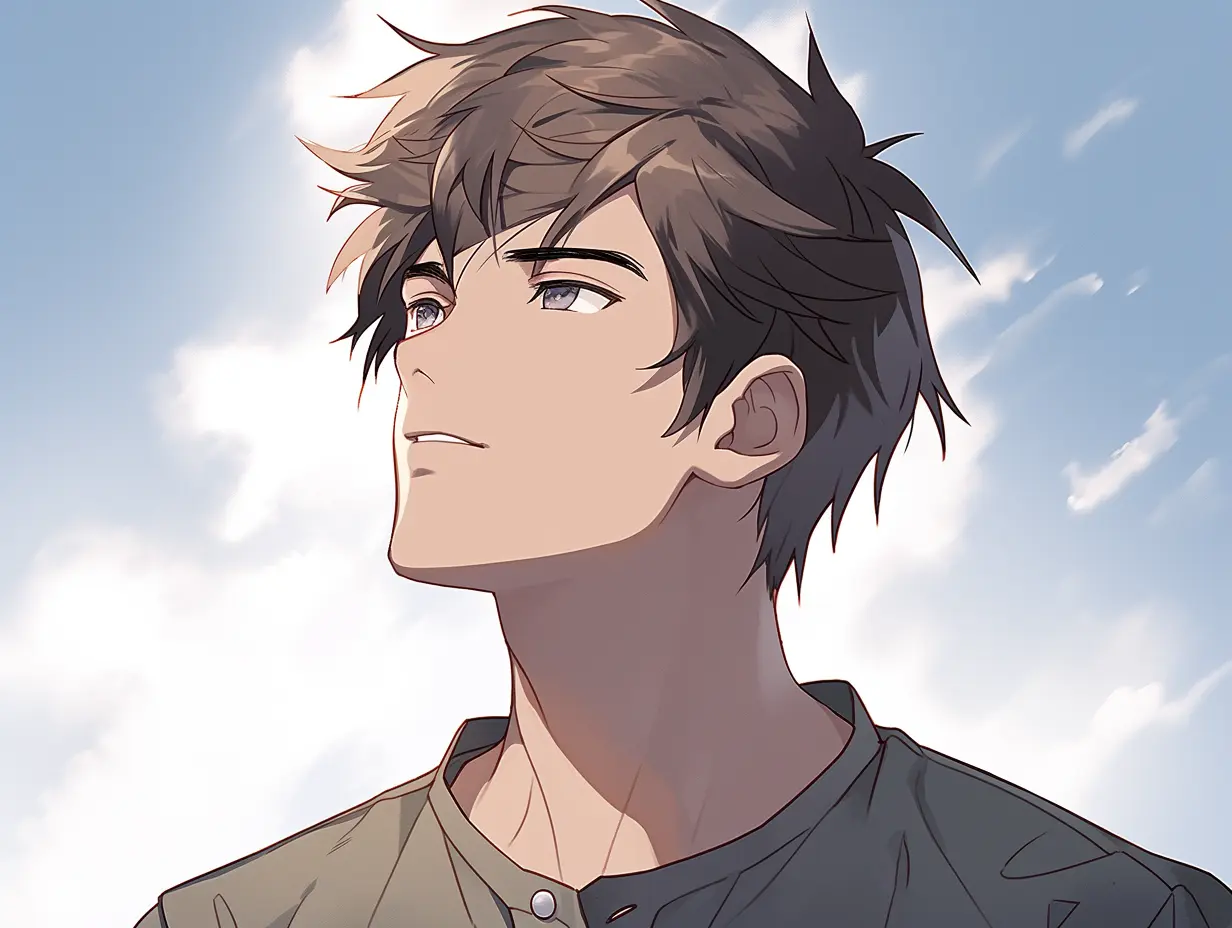
天川は、驚くほど博学で、質問に回答するだけでなく、捕捉説明もしてくれた。
例えば、真面目な人が陥りやすい罠や「いい人」ほど損をしてしまう仕組みなど。
後から気付いたのだが、これはすでに天川によるカウンセリングだった。
宗太郎にとっては、目から鱗がボタボタ落ちまくる体験だったが、天川に心酔したのは間違いない。
だからこそ、将来への思いを強くしたのだった。
【今後、俺が頼るべきは心理学!】


敬愛する天川から教えを受けた大学生活。
それはまさに、光陰矢の如しだった。
心理学の基礎もカウンセラーとしての土台も天川に叩きこまれたが、宗太郎にとっては全てが新鮮で、自分の心も満たされるものだった。
理系の頃は、エセ科学とバカにしていた心理学やカウンセリングにも、いくつもの流派があることを知った。
それはつまり、多くの人達が真剣に取り組んでいる証明にもなる。
哲学的で教育的でもある「天川のやり方」は、実はやや異端だった。
宗太郎がそれに気付くのは、大学を卒業してからなのだが、今の宗太郎にドンピシャだったのは幸運だった。
逆に、カウンセリング協会会長である東雲陽光の書籍や論文は、王道であるにも関わらず、何度目を通してもしっくりこなかった。
いずれにせよ、宗教も哲学も占いも合わなかった宗太郎を救ってくれたのが心理学。
それがとてもありがたかった。


1992年。
すでに宗太郎が大学を卒業し、カウンセリング活動を始めて5年が経っていた。
自分で上手いとは思わなかったが、せめて最大限の誠意を携えてクライエントと向き合うことを心掛けてきた。
ちなみに周りからは「モノ言うカウンセラー」として、いい評価も悪い評価も受けていた。
やはり天川の弟子ということもあり、王道からは少し外れていたのだ。
8月2日。
卒業後も、毎年、顔を出している天川ゼミ合宿。
そこへ今年は、妻となった彩子を連れて参加した。
彩子も同じ大学の心理学部卒。
別のゼミ所属だが、天川とも古い付き合いとなっている。
天川は、宗太郎を見るなり愚痴をこぼした。
「お前の悪評はどうにかならんものか? 世間では完全にヒール扱いじゃぞ」
「世間からというより石川慶之からですよね。あいつは昔から俺を目の敵にしているんです」
彩子がやんわり助け舟を出してくれた。
「石川さんは、協会長である東雲さんの愛弟子ですからね。どうしても向こうが正論になりがちですよね…」


天川は首をゆっくり横に振った。
「そうじゃが、先日は協会から直接、嫌味を言われたわい。天川さんはカリスマ・カウンセラーを量産するつもりですか?とな」
ここまで大人しく聞いていた、ゼミ生の鈴原香織が口を開いた。
「わお、カリスマ? いいじゃないですか。私も先輩に続きまーす!」
彩子が優しく微笑んだ。
「いい? 香織さん。カウンセラーにカリスマ性は不要なのよ。カウンセラーはクライアントと同じ目線で進んだり、下から支える存在だから」
「はぅ…」
「対してカリスマは、リーダーみたいに上から引っ張りあげる人のための言葉だから…」
「ハイっ!分かりました!」
香織が勢いよく右手を挙げた。
「つまり『勘違いするな、調子に乗るな、このボケ野郎っ!』って意味ですね!」
「最後のボケは余計だろ」
いつもの香織節に宗太郎は苦笑した。
「おー先輩、これがホントのボケ突っ込みてすかー」
「いや違うから…」
宗太郎と彩子が同時に突っ込んだ。
香織のこの屈託のない明るさが、悩み多き心理畑の人間達にとっては癒しでもあった。


1994年10月18日。
K島グランドホテル。
天川玄作のこれまでの功績に対して文部科学省から賞が贈られた。
今日は、そのお祝いの席だった。
宗太郎をはじめ、心理学関係者が大勢見守る中、天川が淡々と言葉を続けた。
そして、スピーチも後半に入った頃だった。
「私は初めて、今回の勲章を誇ろうと思います。これまで皆さんと作り上げてきた栄光を受け入れようと思います。自分を誉めてあげようと思います」
確かに天川らしくない言葉だと思っていた。
が、突然、並んで聞いていた妻の彩子が泣き出したことに驚いた。
「え? 彩子どうしたの?」
「先生が、今、過去の栄光にすがるって…」
「うん、だから?」
「だから? もう先へは進まないということでしょ…」
「なるほど。つまり?」
「あなた本当に分からない人ね。カウンセラーとして大丈夫? このスピーチは先生の引退宣言に変わったのよ!」


天川の授賞式が終わると会場は懇談会へと移行した。
和やかな中にも天川の引退を察する人間も多くいて、どこかしんみりともしていた。
宗太郎も動揺を抑えきれないまま、方々へお礼の挨拶回りを続けていた。
そして次は、協会長である東雲陽光と懐刀の石川慶之の番だった
「東雲先生、本日はご足労ありがとうございます」
宗太郎が頭を下げると、隣の石川が皮肉混じりの口を開いた。
「高見先生から挨拶とは珍しいですね」
「そんなことはないでしょう」
宗太郎は苦笑した。学会でも石川から誉められたことは一度もない。
「石川先生、私は東雲先生も天川先生も大変尊敬していますので…」
すると意外にも東雲が口を動かした。
「それは少し問題発言だな。間違えないでくれたまえ。天川玄作を一番尊敬しているのは私だよ」
「はぃ?」
宗太郎は驚きを隠せなかった。
「それにしては、メディアでも学術誌でも、ずーっと否定されていたようでしたが…」
「ふむ。君にはそう見えていたか…。高見君、テーゼを否定することを何と言う?」
「アンチテーゼです」
「では、そのアンチテーゼを繰り返した先には何が生まれる?」
「争いや戦争ですか?」
「最も愚かにやればな。建設的に進めていけばどうなる?」
「…」
答えられない宗太郎を見かねたのか、石川が口を挟んできた。
「ふぅ…。ジンテーゼですね」


「ジンテーゼ…」
宗太郎にとっては聞き慣れない言葉だったが、東雲は満足そうに頷いた。
「まぁそういうことだ。同意からは安らぎに似た安心感が生まれる。しかし、それでは大きな進歩、発見は望めないのだ」
「つまり、天川先生と会長は、アンチテーゼをキャッチボールする厳しい関係だったのですか?」
「日本はカウンセリングの分野において後れをとっている。のんびり仲良くというわけにはいかなかったという話さ」
「天川先生はこのことを?」
「今から20年前、私から天川に提案して、彼も快くその役割を引き受けてくれたよ」
「では、お二人の仲は?」
「君も話が分からない男だね。嫌い合っているわけがないじゃないか。学生時代からの親友だよ。そして今日まで、ずっと戦友でもあった…」
いつしか東雲は優しい眼差しに変わっていた。


宗太郎は、このパーティで、様々なことに気付かされた。
いや、これほど自分の能力の低さを痛感したことはなかった。
【俺は玄作先生にずっと甘えていたのか…】
天川の秘蔵っ子ともてはやされることに胡坐をかき続け…。
そして師匠が引退するとなって、初めて自分に危機感が生まれた。
今のままでは石川にライバルとさえ思われない。
ましてや天川玄作の後継者など…。
【このままではいけない…】
危機感は焦燥感に変わっていた。
今すぐにでも何かをしたい衝動だった。
気付けは宗太郎は、東雲に対して下げられるだけ深く頭を垂れていた
これまでの東雲に対する自分の器の小ささを恥じる意味合いもあったかもしれない。
【今の俺がすべきなのは…】
「東雲先生。不躾ではありますが、お願いがあります」
宗太郎は、昨日までの自分には想像できない言葉を口に出した。
「どうか私にスーパーヴィジョンをして頂けないでしょうか?」
石川の、驚愕と嫉妬と恐怖にいりくんだ表情は…、ひとまず放置しよう。
そう。この日から、本当の意味でのプロカウンセラー「高見宗太郎」が再スタートするのだった。
-fin-



そうですよね。高見先生も最初から「分かる男」ではなかったわけですよね



長老にもこんな若い頃があったんですね。これは貴重なお話でした



分かり難い心理学用語も解説して頂けて、大変ありがたいです

