
ちなみにミーティングは、クリエイティブを仕事にしている、この3人で行います。
日々、文章ばかりを書いている私、「三笠哲也」と…
 毛利悠介
毛利悠介自由気ままなエンジニアの「毛利悠介」と…



ギャグ&WEBデザイナーの「あ・たい」ですね
それぞれ分野は違いますが、「クリエイティブあるある」や「クリエイターならではの苦労」などもご紹介できればと思います。
それでは早速、いってみましょう!



誰か彩美さんに突っ込んであげてーっ!
- とっさのアドリブが苦手な人
- 問題解決能力を上げたい人
- 新しい商品開発やサービスを生み出したい人
- クリエイティブな趣味や仕事を持ちたい人
- アイディアマンになりたい人
- ひらめく毎日にトキメキたい人
今日からクリエイティブになろう!
1:ひらめきとは何か?
皆さんにとって「ひらめき」とは何ですか?
私にとっては、突然、頭に浮かぶ言葉です。
ライティングの作業は、言葉が出なくなったら終わりですから、ひらめきは大切な相棒ですね。



私は、イメージが形となって降りてくることがひらめきです。
ちなみにアシスタントで最初にひらめいたキャラクターはハッチです。



どうもーっ!



僕は、よりベターな方法が直感的に分かることですね。
僕の仕事は、常に正しいルートを探しながら作業しているようなものなので、素晴らしい方法を思い付いた時などは、小躍りしますね
なるほど。
ひらめきの中身はそれぞれですが、予期せぬ瞬間にやってくるのは共通ですね。
また、過程を飛び越えて、いきなり答えだけが示されるのも同じです。



ですから、「なぜそれをひらめいたか?」と聞かれても困ってしまいます



でも本当は、何もないところからやってくるわけではないのですよね
はい。ここは多くの方が勘違いをされていますが、重要なポイントです。
何も無いところから、突然、アイディアがひらめくことはないのです。


「無」から「有」は生まれません。
意識できない「有」の組み合わせのために、あたかも無から閃いたと感じてしまうのでしょう。
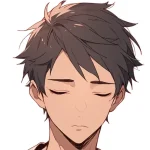
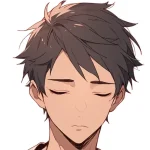
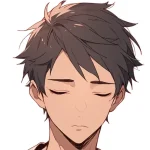
うーん、ちょっと僕には難しい話となりますね。
既存の有の組み合わせならば、斬新なアイディアは生まれてこないのではないでしょうか?
ひらめきは、もっと自分を超えた神秘の力だと思うのですが?
確かに、どんなに優れたクリエイターでも、意識できる「有」などちっぽけなものです。
ブレインストーミングの限界は、「意識上」という点にこそあります。
だからこそ「有」の素材は、無意識下に無尽蔵に蓄えられている記憶や知識を使うのです。
それらを組み合わせ、新しい形として取り出す以外、革新的なひらめきは生まれません。
それが「想像」であり「創造」なのでしょう。



無意識って、どうがんばっても意識できません。
だから私達は、神からの啓示のように感じてしまうわけですよ、モーリー



ふむ…。「ひらめきって自分の無意識からのメッセージ」なのですね。
恥ずかしながら、今、初めて知りました



ドンマイペー(Don’t my pace)
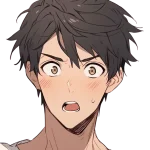
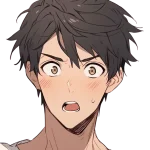
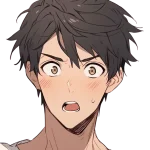
そこはドンマイ(Don’t mind)でいいじゃないスかー。
マイペース禁止って…
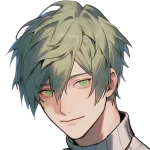
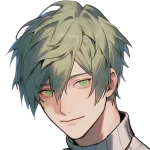
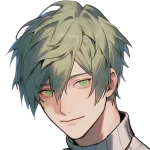
ふふっ…
2:ひらめきが起こるプロセス



ひらめきには、以下のステップが含まれます
テーマに関連する情報を集め、脳にそれらの知識をストックする期間です
実際に頭を使って、アイディアを生み出す作業を行う期間です。
有名なやり方としては「ブレインストーミング」が挙げられます
いいアイディアが出ても出なくても、一旦、考えることを止める期間です。
テーマからは離れるのですが、無意識下では作業が継続しており、新たな組み合わせを探しています。
無意識下で出た答えが意識上に現れる瞬間です。
ただし、これは必ず現れるわけではありません。出現条件があるため、一生気付けないで終わることもあります



にゃるほど。こうなっているのかぁ
では、ここから各ステップの詳しい解説をしていきますね。
インプット期間
<仕込みの重要性>
「いいアイディアを出そう」と意気込んでも、ひらめきはなかなか生まれません。
まずは、いい素材(有)をたくさん用意する必要があるのです。
無から有は生まれず、有があるほど組み合わせのパターンが増えるからです。
知識や情報は、あればあるほど有利です。
たとえテーマに関連しなくても、あった方がひらめきは起こりやすくなります。
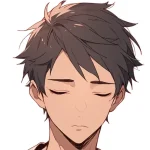
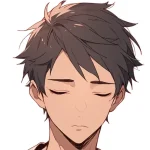
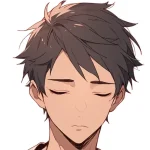
うーん、むしろテーマとは異なる分野の知識があったほうが、革新的なアイディアにつながるイメージがありますね。
科学、アート、歴史、哲学…、多種多様な分野を積極的に学ぶことで、新しい視点が生まれやすくなるのではないでしょうか



いずれにせよ、たくさんのネタを頭の中に放り込むことですね。
私もデザインには人並み以上に触れてきた自負があります
確かに私も小さい頃から本をたくさん読んできましたね。
読書でもセミナーでも交流会でもネットでも、方法はいくらでもあります。
脳を刺激し、ひらめきにつながる有用な情報をどんどん自分の中にインプットしていってください。
脳は無尽蔵なので安心して下さい。
溢れだすこともこぼれ落ちることもないので、どんどん入れていきましょう。



忘れてしまうのは、意識上の話で、無意識下には、必ずストックされています



まずは素材集め!それを忘れないで下さいね



えーと、肉じゃが、かぼちゃのうま煮と…



それは惣菜集め!




記事全体の4分の1に到達しました。
あなたの知識を得ようとする姿勢が本当に素晴らしいです!
ただ、先は長いので、疲れたら休憩してくださいね
アウトプット期間
ここでは、実際に頭を使ってアイディアを生み出す作業を行います。
素材を入れれば勝手に出来上がるわけではありません。
まずは、意識的に頭を使って「ひらめき」に火をつけなくてはならないのです。



アイディアを出すには、既存の概念に縛られず、独自の視点や発想を持つことが大切でしょう。
常識を疑い、逆の立場や視点から考えると斬新なアイデアが出やすくなります



モーリーの発想は独特すぎて、変人扱いされることもあるものね。
でも変人って、クリエイターにとっては最高の誉め言葉かも



ギャラクティックサンキュー!
ちなみにビル ゲイツは、「初めは人に笑われるようなアイディアでなければ、 独創的な発想をしているとは言えない」とまで言っています



なるほど&私のギャグ取るな
さーて、アイディアを出すテクニックとして「ブレインストーミング」が挙げられますが、まずはこの説明をしましょう。
①自由にアイデアを出す
②出てきたアイデアは批判しない
③アイデアは質より量。出てきたアイデアから連想して、さらに量を出す
④アイデアを組み合わせていく
この流れで「いい案」が出やすくなります。
ブレインストーミングで求められているのは、あくまでアイディアです。
ひらめきはハードルが高いですが、アイディアなら努力次第で、いくらでも出せますからね。



もちろんアイディアを絞りだそうと努力している内に、いいひらめきが生まれることもありますよ
ブレインストーミングは、集団でも1人でもできます。
私と星野さんはスタッフがいるので外部からのアイディアも取り入れられますが、毛利君は1人で量産してしまうのが凄いところです。



僕には元々、妄想癖があったことも幸いしたのでしょう。
小さい頃は、思いついたことを机や壁に書いては、よく親に怒られていましたから。
正直、アイディアはいくらでも出せますよ
妄想癖のある人は有利ですねw
逆に、アイディアが全然出てこないという方もいることでしょう。
そんな時、皆さんはどうしていますか?
私はブレインストーミングを行う前に瞑想をするようにしています。
心が落ち着き余計な雑念が消えるので、純粋にアイデアが浮かびやすくなりますよ。



瞑想はしたことがありません。余計、迷走しそうなのでw
マインドフルネスとしては、BGMの工夫でしょうか。
私はクラシックを流しながらブレインストーミングを行うので、そこでスイッチが入る感じです



僕はどちらもやりません。
やりたくない時はやらない主義なので、わざわざ瞑想やマインドフルネスは必要ないんですw
ですから、やっている内に夢中になって入り込んで、自然とその集中状態に入る感じですかねー
それぞれやり方はあるようですが、まずは自分の頭の中でしっかり汗をかくことが大切です。
ひらめきという不確定要素に頼っているだけでは仕事になりませんので、アイデアを出すのは必須です。
ひらめきはプレゼント程度に考えておきましょう。



ヒラメ筋のプレゼント?



それはふくらはぎの筋肉ですよ~
熟成期間
頭をたくさん使ったならば、テーマについて考えることを一時的に止めましょう。
これは単なる休息でも気分転換でもありません。
「止めることでひらめきが生まれる余地をあえて作る」のです。
考えることを止めても無意識下では並列的な処理が働くため、むしろひらめきが出やすくなります。
これを「インキュベーション効果」と呼びます。



そうそう、インベーダーゲームね!



絶対分かってないでしょ
真面目な人や心配性な人ほど、いつまでも物事を考え続けてしまいがちですが、それは逆効果ですよ。素晴らしいひらめきを得るために、あえて離れることも大事にして下さい



あんたのことだニャン



ハッ!
収穫期
収穫期と書いてありますが、ひらめきを必ず収穫できるとは限りません。
いつ収穫できるかも分からないため、ステップ1から3を繰り返しながら、ひらめきが訪れるのをひたすら待つことになります。



私、まーつーわ♪



100%歌ってくれると信じてました
ちなみに、ひらめきが訪れるタイミングや場所は、全くバラバラで予測不可能です。
それでも環境によって頻度に差が出ることは明らかになっていますので、私達は、環境を整えて待つことにしましょう。
<ストレスがかかっている状態>
心理的なストレスがかかっていると、脳の優先順位がストレスの対処に向かいますので、まずひらめきは訪れません
<言葉に意識が集中している状態>
読書や歌詞のある音楽を聞いている時は、脳のワーキングメモリに負荷がかかるので、ひらめきが起きにくくなります
ひらめきやすい環境
リラックスできる快適な環境に自分を置くことで、ひらめきを手にする機会が増えます。
完全に静かであるよりは適度に音があった方がよく、人工物に囲まれるよりは自然を感じられる環境のほうがひらめきやすくなります。
参考までに、偉大なひらめきが起きた時の状況を紹介しますね。
・化学者ケクレが、化学式である「ベンゼン環」をひらめく
・ノーベル物理学賞の湯川秀樹が「中間子論」を思いつく
・ポール・マッカートニーに「Yesterday」のメロディーが思い浮かぶ
・小説家のJ.Kローリングが「ハリー・ポッター」のアイデアをつかまえる
・哲学者カントは、 毎日決まった時間に、決まった歩調で散歩をして「純粋理性哲学」を記した
・「哲学の道」を書いた西田幾多郎の散歩コースは、そのまま「哲学の道」と名付けられている
・アルキメデスは、お風呂の中で「浮力の原理」を発見した



さーて今日は、どこでひらめきを待とうかなぁ?
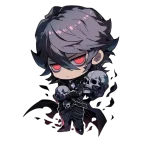
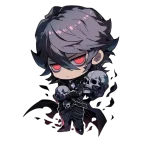
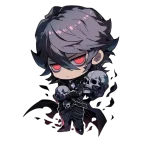
そんだけ毎日リラックスしてて、まだひらめかないの?


あなたも、ひらめきが生まれやすい場所で待って、うまく収穫してくださいね。




わーぃ!この記事も半分まで来ましたよー!
ここで一区切りもいいですね♡
あなたのやる気の高さに感動しています!
3:ひらめきを手にするための工夫5選
工夫①
遊び心を忘れず、失敗を恐れない
経験や知識、即ち「有」に劣る子供が、大人顔負けの素晴らしいアイディアを出すことがあります。
これはまさに、失敗を恐れず遊び心を持った柔軟な発想があればこそでしょう。
このテーマ、私は苦手なのですが、毛利君は大得意ですよね。



遊び心は、僕の唯一の取り柄みたいなものですね。
仕事をしていても自由連想が膨らみ過ぎて、どんどん脱線していくんですぅー
でも、脱線したからといって戻らないんですよね?



そのまま進むと、思いもよらずクリエイティブなものが出来上がりますからw
三笠さんの小説でも、スピンオフものって遊び心からの脱線ですよね?
まぁそうとも言えますね。
そして失敗を恐れないと言えば星野さんです。彼女のすべってもギャグを言い続けるメンタルの強さは誰もが認めるところでしょう。



あれ? デザインじゃなくてギャグのお話ですか?
確かに笑いもクリエイティブですけど…外すのを怖がっていたら何もできません。
みんなー!私達にもっと温かい目をーっ!
2人に限らず、世の中には、柔軟な思考で成功した例がたくさんあります。
以下に、失敗作を発想の転換で人気商品に押し上げた例を挙げていきますね。
<商品A>
本来の目的は、強力な接着剤でした。
失敗して弱い接着剤ができ、ポストイットが誕生しました。
<商品B>
本来の目的は、心臓病の治療薬です。
副作用として、勃起不全に効果があることが発見され、バイアグラとして売り出されました。
<商品C>
本来の目的はマグネトロンの研究でした。
研究中、チョコレートが溶ける現象に気づき、電子レンジが生まれました。
<商品D>
本来の目的は、頭痛薬です。
しかし清涼飲料水のほうが向いていると判断され、コカ・コーラと名付けられました。



面白いですわね



「失敗とは、別の面から見た成功である」



誰の名言?



僕。今ひらめきました



ずこーっ!
工夫②
他者からのフィードバックを受ける
あなたは自分のアイデアに対するフィードバックを他人に求めていますか?
もちろん、良いフィードバックもイマイチなフィードバックもあるでしょう。
私は、スーパーやスポーツ施設で「お客様の声」コーナーをよく覗き込むのですが、中にはムチャクチャな要求もあるのです。
ダメ出し続きでは、メンタル的にもたない人もいるでしょうから無理強いはしません。
やるかやらないかは自由ですが、新しい素材が加わることで思いがけない化学反応が起きることがあるので「ひらめき」に関してはおすすめですよ。
工夫③
ひらめきが出やすいモードに入れる
皆さんはひらめきが出やすい自分のモードを把握していますか?



経験的に、何となくは分かります。
逆に、アイディアが出てこない時は、頭を逆さに振っても無理なのも…



自分で上手く「出る出るモード」に入れられれば苦労しませんよね
そんな皆さんに朗報です。
ひらめきの出やすい脳波は、シータ波であることが確認されました。
ですから、自律訓練法などを応用して、自分の意思でシータ波を出せるようになれば、クリエイティブな作業は捗ることになります。



シータ波って、アルファ波よりも深いリラックス状態で観察される脳波ですよね。
ほぼ寝る寸前で、「まどろみ波」とも呼ばれているじゃないですか?



三笠さんが瞑想をする理由はそれだったのですね。
ただ、僕達は無理ですね。シータ波までいったら、爆睡一直線です。



一緒にするニャー!
実は、もう1つシータ波には面白い特徴があります。
好奇心が刺激された時にも強く出るそうです。
毛利君が色々な発明をするのは、日々、何事にもワクワクと興味を持ちながら取り組むからなのでしょう。



へぇー。あの感覚がシータ波ならば、僕はそれを再現するのは難しくありません。
問題は、気持ちが乗らないと、全く動けないことです



しょっちゅう納期を破っているものねー
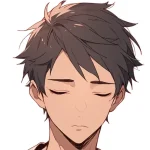
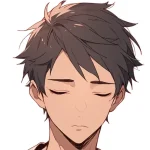
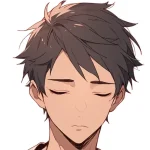
はい。社会人失格なのは、自分でもよく分かっています…
逆にシータ波の大敵は「マンネリ」だそうです。
年を重ねてアイディアが出にくくなっている人は、おそらく日常に慣れすぎて、脳がマンネリ化してしまっているのでしょう。



マンネリ化は、色々な意味で嫌ですね。
ちなみに私は、同じ場所に行く時でも、前回と同じ道は使わないというマイルールを設けています
なるほど。私も「新しいもの好き」ですし、クリエイティブを目指す人間は、自然とマンネリを防ぐ生活習慣を持っているのかもしれませんね



はい。それにしても、アイディアが出やすいモードがシータ波であることが知れたのは収穫でした



将来、クリエイターが脳波計を着けるようになるのは間違いないでしょう。着けさせられるのは嫌ですけど
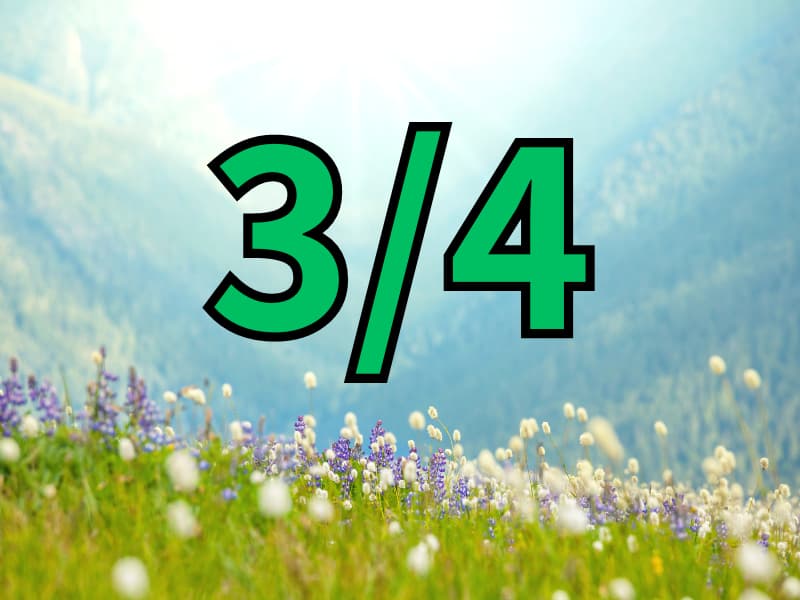
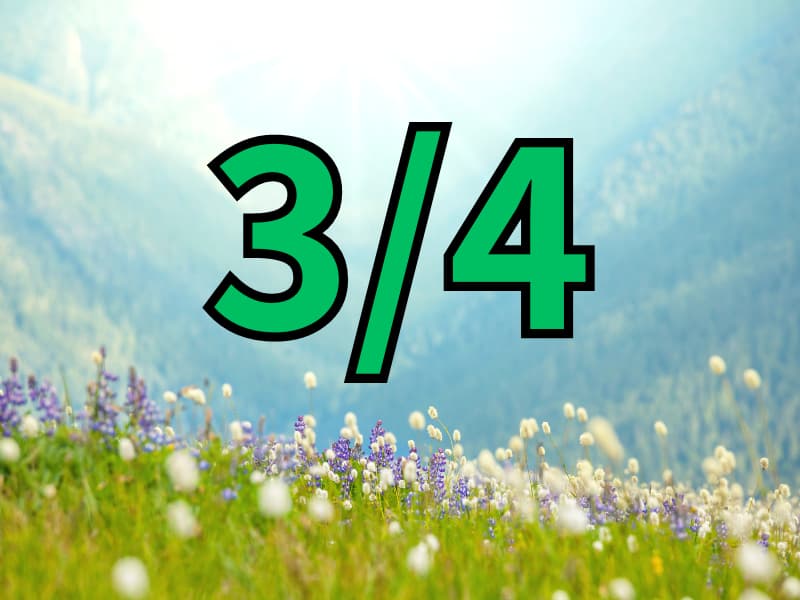


記事全体の4分の3まできました!
がんばりましたね。ここまでのあなたに拍手です。
ゴールはもう目の前ですよーっ!
工夫④
思い出す感覚を大事にする
私は、クリエイティブな作業とは『無意識の中にある知識と記憶を思い出すこと』と考えています。



ん?



ん…
分かり難い表現で申し訳ありません。
無意識にある「有」を取り出す作業とは、「思い出す」感覚に近いと思うのです。
ちなみに自分の無意識だけでなく、集合無意識からも取り出せるようになれば、それこそ毛利君が初めに言っていた「自分の枠を超えた革新的なひらめき」になるでしょう。
まだ私に、そこまでの感覚は掴めていませんが。



「あ、閃いた!」ではなく、「あ、思い出した!」って感覚が正解ということですか…



集合無意識と言えば、人類のあらゆる知識と経験が詰め込まれているワンダーボックスですよね。そこにアクセスできるのは、神の領域というかノーベル賞クラス…
脳科学的にも、閃きと思い出す作業は近いはずです。
どちらも海馬が深く関わっていますから。
そして、ひらめきが思い出す作業なら、普段から思い出す訓練をすることも、ひらめきが出やすい体質を作るのではないでしょうか?
誰しも「あれ何だっけ?」「えーっとあの人の名前思い出せない」といった物忘れはあると思いますが、そんな時こそ必死で思い出す作業を私はしています。



単なるボケ防止でなく、その脳の訓練が、ひらめきを出しやすくさせるわけですね



誰がボケ老人じゃーい!?
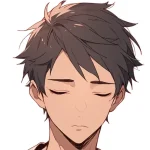
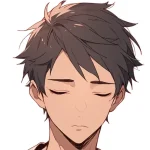
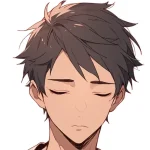
えっと、ここはスルーしましょう。
ちなみに三笠さんは、思い出す訓練ってどんなことをやられているのですか?
脳トレもやっていますが、簡単なのは、前日食べた食事内容を思い出すことですね。
朝昼晩、3食スラスラと出てきた日は、やはりひらめきも起きやすい気がします。



なるほど。
ぜひ皆さんも、思い出す訓練をやってみて下さいねー!
工夫⑤
ひらめきを逃がさずに保管する
誰にでもひらめきは起こります。
ただ残念ながら、せっかくのひらめきを逃してしまうことがあるのです。
いや、普通に生活している限り、逃すことのほうが多いでしょう。
ひらめきは、驚くほどすぐに消えてしまいます。
私など「あーメモしておけば良かったー」と悔やむフレーズが山ほどあります…。
もちろん理想は、ひらめいた瞬間に記録をとることでしょう。
携帯にメモしたり、録音したりすることで、ひらめきの半分は保管できると思います。
ただ、状況によっては携帯を取り出せない場面もありますよね…。



思い付いたことは覚えているけど、内容が思い出せないもどかしさはありますね。
私がギャグをすぐ言ってしまうのは、この反動でもあるのです



逃すくらいなら試したい…というスケ



誰がスケベ根性じゃーい!?
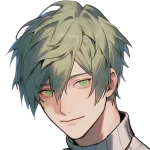
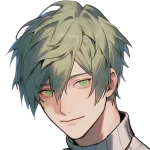
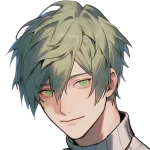
保管はしないのですか?



ウケた時の感覚だけを覚えておくよう心掛けています



僕も基本的には書き留めますが、クライアントと商談中の時などは、頭の中にキーワードだけを記憶させて、後からそれを頼りに思い出すようにしています
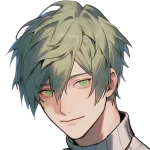
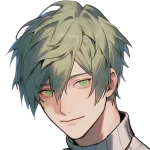
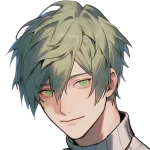
再現率はどれくらいですか?



7割ですね。キーワード自体を忘れることもありますし、仮に「シュークリーム」というキーワードだけ残されても、「何のこっちゃ?」になる時もありますから



プッwシュークリームって…
皆、そのあたりは苦労しているようですね。ただ、せっかく現れてくれた貴重なひらめきですから、これからも大事に保管していく努力を続けましょうね。
4:まとめミーティング
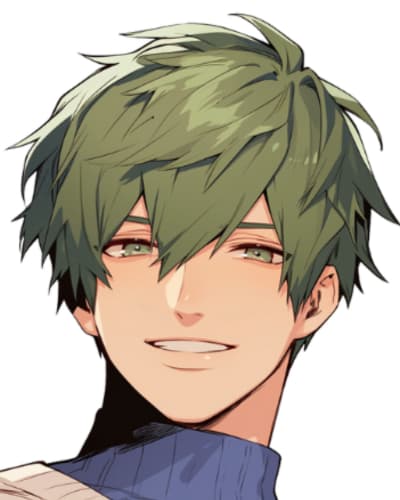
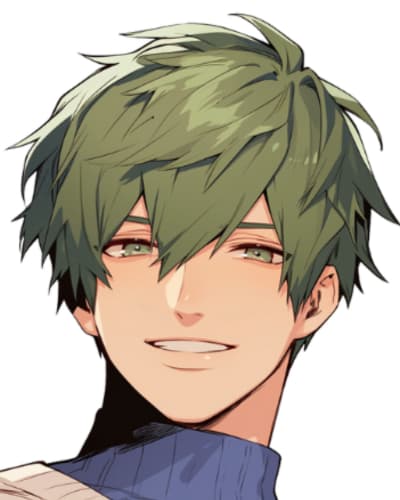
お疲れさまでした!
では最後に、まとめのミーティングをしましょう。



おかげさまで、ひらめきの知識が整理され、正体がよりクリアーになりました!



世間では、クリエイティブな仕事には才能が必要という風潮がありますが、それは関係ないことがよく分かりました。
結局、スキルの話でしたよね。
ですから、誰しも訓練で向上できると思います。
近年の認知科学においては、「ひらめき」は試行錯誤を基にした現象であり、「個人の才能」ではないと結論付けています。



努力というより習慣ですね。連想、インスピレーションを大切にする生活習慣に尽きると思います
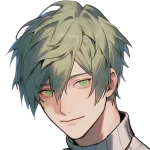
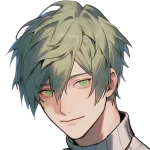
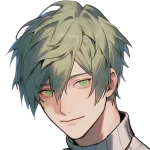
生みの苦しみはありますが、クリエイティブな作業は楽しいですよね



はい。楽しいから続けています



ですね!
ありがとうございます。
おかげさまで上手くまとまりました。
では、ここからは打ち上げです。
皆で〇〇を××しに行きましょう!



いや、ここは逆転の発想で、××を〇〇しに行くのはどうでしょう?



ならばいっそ▲でいくのは?
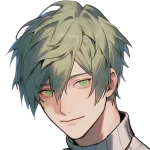
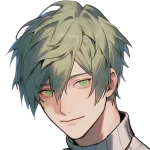
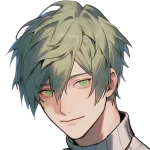
あっ、革新的なアイディアが閃いたっ!



ふぅー、この三人が集まれば、当然こういう展開になりますよねー


では、いよいよお別れですね。
あなたがこの記事を読んで、少しでも参考になる点があったならば幸いです。
そして、最後までお読み頂き、ありがとうございました!
読んでくれる方がいるからこそ、私は書き続けられます。
あなたもひらめきのある人生を楽しんでいってくださいね!
メンバー一同:はばなぃー(^^♪




